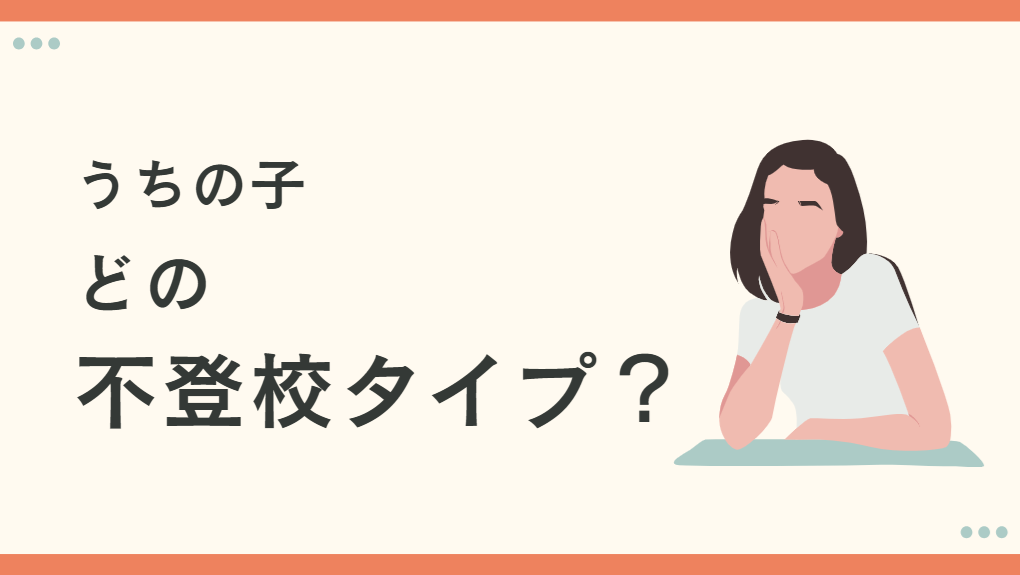「学校に行きたくない」と感じるお子さんは決して珍しくありません。不登校の理由はさまざまであり、無理に登校を促すことが逆効果になる場合もあります。しかし、環境や気持ちの変化によって「もう一度学校に行ってみよう」と思う瞬間が訪れることもあります。
本記事では、小・中学生や高校生が不登校から抜け出したきっかけを紹介するとともに、保護者としてどのような対応をすればよいのかを解説します。
お子さんが前向きな一歩を踏み出せるよう、できることから取り組んでみましょう。
不登校は珍しいことではない
文部科学省の調査によると、不登校の児童・生徒の数は年々増加しており、小・中学生だけでも年間30万人以上が不登校を経験しています。
その背景には、学校生活のプレッシャー、友人関係の悩み、学習の遅れ、家庭環境の変化など、さまざまな要因があります。
とはいえ、お子さんが不登校になると、保護者は「どうしてうちの子だけこうなったのか」と悩み、焦りを感じることも多いでしょう。
「学校に行かせないと将来に影響が出るのでは」「他の子は普通に通っているのに」と、不安が募るのは当然のことです。
しかし、不登校は決して珍しいことではなく、特別なケースでもありません。むしろ、学校という環境がすべての子どもに合うわけではないという事実を、社会全体が理解しつつあります。
何より大切なのは、お子さんが安心して過ごせる環境を整え、心と体が回復するのを待つことです。不登校は「ずっと続くもの」ではなく、時間をかけて心身のバランスを取り戻せば、お子さん自身が新しい一歩を踏み出すことができます。
不登校は決して「終わり」ではなく、お子さんが成長するための大切な過程のひとつ。保護者も「学校に戻さなければ」と思い詰めるのではなく、長い目でお子さんの未来を信じることが大切です。
小・中学生が不登校から脱出したきっかけ5選
不登校からの回復には、それぞれのお子さんに合ったきっかけが必要です。無理に学校へ行かせるのではなく、お子さんの気持ちを尊重しながら、少しずつ前向きな変化を促していくことが大切です。
ここでは、不登校から脱出したきっかけとしてよくある5つの例を紹介します。
きっかけ① 学校環境の改善
学校の環境が変わることで、安心して通えるようになるお子さんも少なくありません。
担任の先生が変わり、安心できる関係が築けた
前の先生とは相性が合わず、話しづらかったお子さんが、新しい先生になったことで「この先生なら安心できる」と思えるようになり、少しずつ学校に行けるようになったケースがあります。
クラス替えで新しい友達ができ、学校に行きやすくなった
前のクラスでは友達ができず孤立していた子が、クラス替えで気の合う友達ができ、学校が楽しいと感じるようになったことがきっかけになることがあります。
いじめやトラブルが解決し、安心できる環境になった
いじめが原因で不登校になった場合、学校側の対応によっては状況が改善し、安心して登校できるようになることもあります。
たとえば、いじめの加害者とクラスが分かれたり、先生がしっかりと見守ってくれるようになったりすることで、再び学校へ行く気持ちが生まれることがあります。
きっかけ② 家庭の理解とサポート
家庭での安心感が、お子さんにとって大きな支えになります。
保護者が「無理に行かなくてもいい」と言ってくれて、気持ちが楽になった
「学校に行かなきゃいけない」と思い込んでストレスを抱えていたお子さんが、保護者に「大丈夫だよ」「今は休んでいいよ」と言われたことで安心し、自分のペースで学校に行く気持ちを取り戻すことがあります。
家での過ごし方が自由になり、ストレスが減った
「家にいるなら勉強しなさい」と言われ続けるとプレッシャーになりますが、保護者が家での過ごし方を自由にさせることで、心に余裕が生まれ、自然と学校へ行く流れになったというケースもあります。
家庭学習や習い事を通じて自信を取り戻し、学校に行く気持ちが芽生えた
学校以外の場所で成功体験を積むことが、自信につながることもあります。
たとえば、ピアノなどの音楽や地域のスポーツ教室、オンライン学習などで、お子さんが「自分にもできる!」という実感を得ることで、学校へ行く勇気が湧いてくることがあります。
きっかけ③ フリースクールや適応指導教室に通った
学校以外の学びの場を活用することで、少しずつ登校できるようになるケースもあります。
学校以外の居場所を見つけることで、人と関わることに慣れた
フリースクールや適応指導教室では、学校とは違う自由な雰囲気の中で学ぶことができ、無理なく社会とのつながりを持つことができます。
そこでの経験を通じて「また学校に行ってみようかな」と思えることもあります。
「ここなら安心できる」と思える環境で学びを続け、少しずつ登校できるようになった
フリースクールで安心して学ぶうちに、自信を持ち、徐々に学校へ行けるようになったケースもあります。「無理せず学び続けること」が大切なポイントです。
きっかけ④ 友達やきょうだいの存在
身近な人の存在が、登校のきっかけになることもあります。
仲の良い友達やきょうだいが励ましてくれた
「一緒に行こうよ!」と声をかけてくれる友達やきょうだいがいると、少しずつ学校に行く気持ちが芽生えることもあります。
久しぶりに友達と遊んで楽しくなり、学校へ行く気持ちが戻った
学校以外の場所で友達と遊ぶ機会があると、「またみんなと一緒にいたいな」と思えるようになることがあります。
きっかけ⑤ ふとした出来事
日常生活の中のふとした出来事が、学校に行くスイッチを入れることもあります。
学校行事や修学旅行に参加し、「やっぱり楽しい」と感じた
修学旅行や運動会などの学校行事に「参加してみようかな」と思えたことがきっかけで、そのまま登校を再開するケースも少なくありません。
好きな授業や活動だけでも参加し、徐々に登校できるようになった
いきなり毎日登校するのはハードルが高いものですが、「好きな授業だけ行く」ことから始めることで、少しずつ学校に慣れることができます。
好きな授業がない場合は、休んでいる期間があっても参加しやすい体育や図工、音楽などの教科から登校し始めるのもおすすめです。
先生や保護者から「無理せず一歩ずつでいい」と言われ、気持ちが楽になった
保護者や先生が「無理しなくていいよ」「一歩ずつでいいよ」と言ってくれたことで、プレッシャーが減り、登校する気持ちが芽生えることもあります。
高校生が不登校から脱出するきっかけ6選
高校生の不登校は、進学や将来のことを考える時期と重なるため、お子さんの「不登校状態の現状」だけではなく、「これから」にも焦りや不安を感じることが多いものです。
しかし、実際にはさまざまな方法で自分に合った道を見つけ、不登校を乗り越えている人がたくさんいます。
ここでは、高校生が不登校から脱出するきっかけとなった6つのケースについて詳しく解説します。
きっかけ① 環境を変えた
高校の環境が合わないと感じている場合、学校の枠にとらわれず、自分に合った学び方を選ぶことで状況が大きく変わることがあります。
通信制高校や定時制高校に転校し、自分のペースで学べるようになった
毎日通うことが負担だったお子さんが、登校日数が少ない通信制や、夜間に通える定時制高校に変えることで、無理なく学習を続けられるようになるケースがあります。
フリースクールやオンライン学習を利用し、学校以外の学び方を見つけた
学校の授業に縛られず、自分の興味のある分野を学べる場を見つけたことで、学ぶ楽しさを取り戻し、前向きになれることもあります。
「高校に行かないといけない」という考えをやめたことで、気持ちが軽くなった
「高校卒業=普通の道」と思い込んでいると、登校できない自分を責めてしまうこともあります。しかし、高卒認定試験や通信制など、さまざまな選択肢があることを知り、気持ちが楽になることで前向きになれることもあります。
きっかけ② 進学や将来の目標ができた
お子さんに将来の目標ができると、「このままではいけない」と思えるようになり、勉強や学校への意欲が戻ることがあります。
「大学に行きたい」「資格を取りたい」と思い、勉強に意欲が戻った
「好きな分野を学びたい」「専門的な仕事に就きたい」と思うようになり、大学進学や資格取得に向けて行動を始めるケースがあります。
やりたい仕事が見つかり、「高校卒業が必要」と考えるようになった
「この職業に就くには高校を卒業しておいた方がいい」と考えたことで、学び直す決意をした人もいます。
自分の好きなことを伸ばすために、新しい道を模索し始めた
例えば、「デザインの仕事がしたい」「プログラミングを極めたい」「プロのスポーツ選手を目指したい」など、学校の枠を超えて好きなことを追求するうちに、自分の進む道が見えてくることがあります。
きっかけ③ 友人や理解者との出会い
不登校状態で孤独を感じていたお子さんが、理解者と出会うことで気持ちが楽になり、前向きな行動ができるようになることもあります。
不登校経験のある先輩や友達と話して、「自分だけじゃない」と安心できた
同じ経験をした人と話すことで「自分だけじゃない」と感じ、心が軽くなることがあります。
アルバイトや習い事で出会った人とのつながりが、自信につながった
アルバイトなど、学校以外の場所で人と関わる機会が増え、自分を受け入れてくれる人と出会うことで、少しずつ自己肯定感が高まり、登校への意欲につながることもあります。
スクールカウンセラーや先生が親身に相談に乗ってくれて、気持ちが楽になった
誰かに悩みを打ち明けることで、精神的に落ち着き、少しずつ学校に戻れるようになることもあります。
きっかけ④ 家族のサポートと考え方の変化
家族の理解やサポートがあることで、安心して次の一歩を踏み出せるようになります。
保護者が「学校にこだわらなくていい」と言ってくれて、気持ちに余裕ができた
「行かなきゃダメ」と言われ続けるとプレッシャーになりますが、「無理しなくてもいいよ」と言われることで、気持ちに余裕が生まれ、自分のペースで行動できるようになることがあります。
家庭でのコミュニケーションが増え、安心して過ごせるようになった
家族と過ごす時間が増えることで、心が安定し、学校へ行く気持ちが芽生えることもあります。
不登校について理解のある支援機関に相談し、新しい道を見つけた
保護者がカウンセラーや支援団体とつながることで、お子さんに合った選択肢が見つかることもあります。
きっかけ⑤ 生活リズムや体調の改善
生活習慣が整うと、気持ちが前向きになりやすくなります。
昼夜逆転を直したら、気持ちが前向きになった
夜遅くまで起きていると、気分が落ち込みやすくなることがあります。生活リズムを整えることで、気分が安定し、行動できるようになることもあります。
運動や食事を意識するようになり、体調が良くなった
運動や食事の改善で体力がつき、外出や登校のハードルが下がることがあります。
カウンセリングや病院でサポートを受け、気持ちが落ち着いた
精神的な不調を感じる場合は、専門家のサポートを受けることで、気持ちが軽くなり、行動しやすくなることがあります。
きっかけ⑥ ふとした出来事
外的、内的問わず、ふとした出来事が、お子さんに前向きな変化をもたらすこともあります。
文化祭や体育祭などのイベントに参加し、楽しいと感じた
学校行事に参加したことで、「やっぱり学校も悪くない」と思えたことがきっかけになることもあります。
「このままでは後悔する」と思い、少しずつ行動するようになった
ふとした瞬間に「このままでいいのかな?」と考え、勇気を出して一歩踏み出すことがあります。
「自分にもできることがある」と実感した
アルバイトやボランティアなど、社会と関わる経験を通じて、「自分の力でできることがある」と気づき、自信がつくことがあります。
きっかけをつくる親の対応
不登校のお子さんにとって、保護者の関わり方はとても重要です。
保護者の言葉や態度によって、お子さんが安心して前を向くこともあれば、逆にプレッシャーを感じてしまうこともあります。
無理に学校へ行かせようとするのではなく、お子さんが安心して過ごせる環境を整え、前向きな気持ちになれるようにサポートすることが大切です。ここでは、保護者ができる具体的な対応について詳しく解説します。
① お子さんの気持ちを受け止める
不登校のお子さんにとって、保護者に「自分の気持ちをわかってもらえている」と感じることが、安心感につながります。
保護者としては、良かれと思ってつい「気にすることない」「●●してみたら」とアドバイスしてしまうことがありますが、落ち込んでいるお子さんにとってはプレッシャーになることがあります。ただ、「そうなんだね」とお子さんの気持ちを受け止めることで、お子さんの気もちが安定していきます。
「なぜ行けないのか」ではなく、「どうすれば安心して過ごせるか」を考える
「なんで行かないの?」「行けばなんとかなるよ」と責めるのではなく、「学校に行くのが辛いんだね」「今はどうしたい?」と、お子さんの気持ちに寄り添いましょう。
不登校の理由を探ることよりも、今後どうすればお子さんが安心して過ごせるかを一緒に考えることが大切です。
「学校に行くべき」という固定観念を捨てる
「学校に行くのが当たり前」と考えていると、お子さんが不登校になることを受け入れにくくなります。
学校だけが学びの場ではありません。「今は学校に行かなくても、学ぶ方法はたくさんある」と考え方を変えることで、保護者の焦りが減り、お子さんもプレッシャーを感じにくくなります。
② お子さんがリラックスできる環境をつくる
学校に行けない状態が続くと、保護者も不安になり「このままでいいの?」と焦ることがあります。しかし、お子さんにとっては、家が安心できる場所であることが何よりも大切です。
家庭を安心できる居場所にする
お子さんが保護者からのプレッシャーを感じると、家にいても気持ちが休まりません。
「どうして行かないの?」と責めるのではなく、家では安心して過ごせるように心がけましょう。
たとえば、好きなことを楽しめる時間を作ったり、会話の中で「無理しなくていいよ」と伝えたりすることで、お子さんの気持ちが落ち着きやすくなります。
無理に解決しようとせず、お子さんのペースを尊重する
「いつまでこの状態が続くの?」と焦る気持ちをぐっとこらえ、お子さんのペースを大切にしましょう。
「早く学校に戻らなければ」とプレッシャーをかけるのではなく、「今は休む時期」「子どもが自分で動き出すのを待とう」と考えることが大切です。
③ さまざまな選択肢を一緒に考える
不登校=「学校に行かせること」だけが解決策ではありません。お子さんの個性や状況に合った選択肢を、一緒に考えていくことが大切です。
柔軟な学びのスタイルを検討する
学校に行く以外にも、学びの選択肢はたくさんあります。
たとえば、フリースクールなら学校とは違う雰囲気で学べるため、通いやすい場合があります。通信教育などのオンライン学習や家庭学習を取り入れれば、無理なく勉強を続けられることもあります。
また、お子さんの様子を見て別室登校を提案してみるのも良いでしょう。
学校以外の世界を知る機会をつくる
ずっと家の中にいると気持ちがふさぎ込んでしまうこともあります。
外に出ることが負担でない場合は、博物館や図書館、公園などに出かけたり、興味のある習い事を始めたりするのも良いでしょう。
アルバイトやボランティア活動など、社会的な経験を通じて新しい世界を知ることが、前向きな気持ちにつながることもあります。
④ 小さな成功体験を積み重ねるサポートをする
お子さんが「自分は何をやってもダメだ」「学校に行けない自分はダメな人間だ」と思い込んでしまうと、前向きな気持ちになれません。
少しずつ成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻せるようサポートしましょう。
「できた!」という経験を増やし、自信を取り戻せるようサポートする
たとえば、「朝起きて家族と朝食を食べられた」「外に出て散歩できた」「オンライン授業を受けられた」など、小さなことでも「できたね!」と認めてあげることが大切です。
学校以外の活動や習い事を通じて、成長の機会を作る
習い事や趣味を通じて「自分にもできることがある」と感じることで、少しずつ自信がついてきます。
音楽やスポーツ、絵を描くこと、プログラミングなど、お子さんが興味を持つことを一緒に見つけてみましょう。
まとめ:子どものペースで前に進もう
不登校のきっかけや理由はさまざまですが、不登校から回復するきっかけやプロセスもお子さんによって異なります。
「ある日突然、学校に行けるようになった」というお子さんもいれば、「ゆっくりと自信を取り戻しながら、少しずつ学校に戻っていった」というお子さんもいます。また、「学校ではなく、フリースクールや通信教育など別の道を選んだことで前向きになれた」というケースもあります。
どの道を選ぶにしても、保護者が焦って無理に登校を強いたり、プレッシャーをかけたりすると、かえってお子さんが不安を感じ、状況が悪化してしまうこともあります。
「学校に行くこと」だけが解決策ではありません。大切なのは、お子さんが安心して過ごせる環境を整え、お子さん自身が「次の一歩を踏み出してみよう」と思えるようにサポートすることです。
焦らず、比べず、お子さんのペースで少しずつ前に進んでいきましょう。
更新日: 2025/2/26
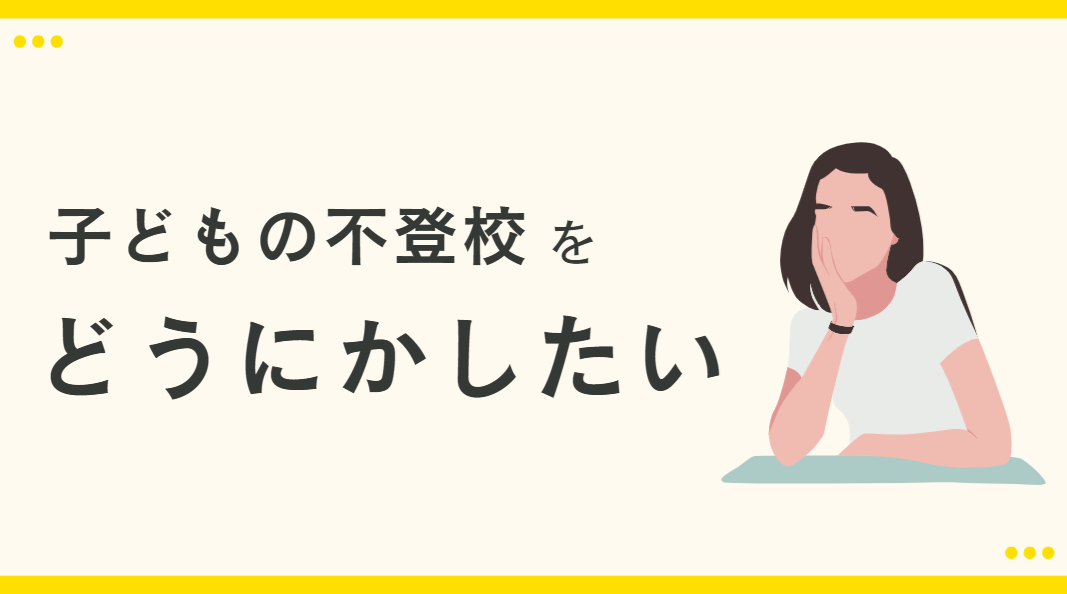

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る