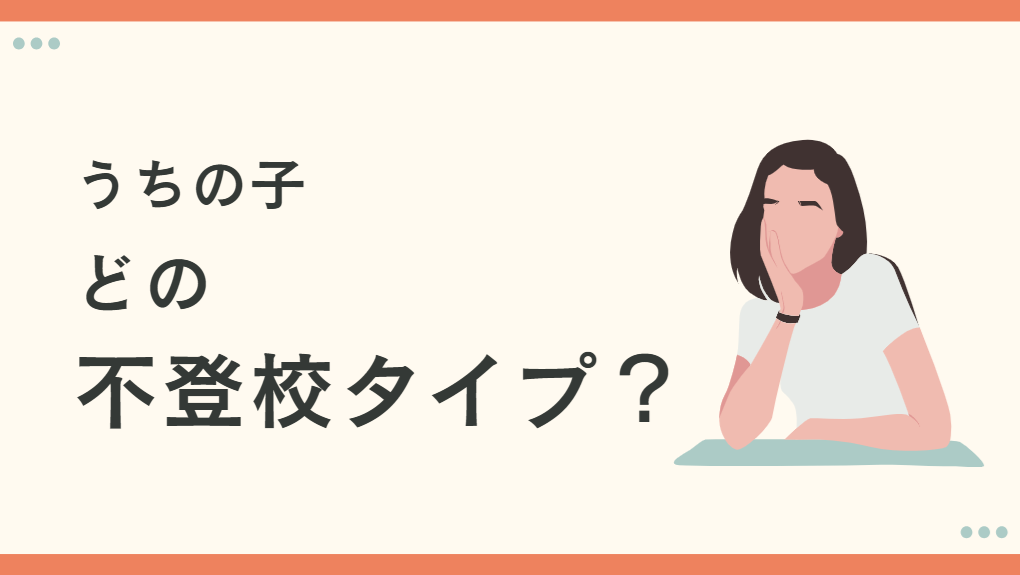日本財団の「不登校傾向にある子どもの実態調査報告書」によると、不登校または不登校傾向にあるお子さんの保護者の回答に「心身・発達上に障害があると診断されている」と回答する保護者も少なくない傾向があります。
「発達障がいのお子さんの不登校」という課題に直面した保護者にとって、日々の接し方や将来への不安は大きな問題です。
発達障がいを持つお子さんが不登校になる原因や、支援の仕方を理解することは、保護者としての負担を軽減し、お子さんにとって安心できる環境を作る第一歩です。
この記事では、発達障がいの特性と不登校の関係性を解説し、発達障がいを持つお子さんが不登校になる原因や家での過ごし方・接し方のポイント、将来の進路について詳しく紹介します。
また、学校でのフォロー体制や、実際に行われている支援事例についても触れ、保護者が利用できる支援のヒントをお届けします。
不登校は「失敗」ではなく、より良い成長のための新たなスタートととらえ、一緒に最善の方法を考えていきましょう。
発達障がいと不登校の関係。不登校になる割合は?
発達障がいと不登校には密接な関係があると言われています。
発達障がいを持つお子さんは、感覚過敏やコミュニケーションの難しさ、注意力の維持が困難といった特性が原因で、学校環境に適応しにくい場合があります。
この特性がストレスとなり、不登校に至るケースが少なくありません。
また、特性を理解されないことで、本人が孤立感を抱いたり、自信を失ったりすることも影響します。
発達障がいを持つ子どもが不登校になる割合
文部科学省のデータによると、2021年度の全国調査で、不登校の児童生徒の約30%に発達障がいが疑われる特性があるとされています。
この割合は年々増加しており、発達障がいの特性が不登校の原因の一つとして注目されています。
ただし、特性が直接的な原因ではなく、学校環境との相互作用が重要な要素となります。
発達障がいが関係する不登校の場合、特性を理解し、お子さんに適した学びの場や支援を提供することが効果的です。
発達障がいの子どもが不登校になる原因
発達障がいのお子さんの不登校は、単なる「登校拒否」ではなく、学校環境や人間関係とのミスマッチ、学習の困難さ、過度なストレスといった要因が複雑に絡み合って起こることが多いです。
そのため、お子さんの特性を理解し、適切なサポートや学びの場を提供することが重要になります。
発達障がいのお子さんが不登校になる主な理由を解説します。
1. 学校環境とのミスマッチ
発達障がいの特性(感覚過敏、注意散漫、読み書きの困難など)に対して学校環境が適応していない場合、お子さんが強いストレスを感じることがあります。
たとえば、音や光に敏感なお子さんは、教室の雑音や蛍光灯の光が苦痛になることがあります。
2. 人間関係の難しさ
発達障がいを持つお子さんは、友達とのコミュニケーションや集団行動が苦手な場合があり、孤立やいじめにつながるケースもあります。
周囲から誤解されやすい特性が原因で、トラブルが生じることが不登校の引き金になることもあります。
3. 学習面の困難
読み書きや計算が苦手な「学習障がい(LD)」や、注意力が散漫になる「ADHD(注意欠如・多動症)」の特性がある場合、授業についていけなくなることがあります。
成績の低下や失敗体験が増えることで、自己肯定感が下がり、不登校になる可能性が高まります。
4. ルールや集団生活の適応困難
発達障がいの特性として、場面ごとに適切な行動をとる「場面適応」が難しい場合があります。
たとえば、規則に従うことや時間通りに行動することが苦手なお子さんにとって、学校生活は負担が大きい場となることがあります。
5. 過度な疲れやストレス
学校生活は、発達障がいのお子さんにとっては「当たり前のこと」でも過度にエネルギーを消耗することがあります。
そのため、家に帰るとぐったりしてしまい、次第に学校に行く気力を失うこともあります。

発達障がいで不登校になった子どもの家での過ごし方
不登校のお子さんは、実は「学校へ行きたい」と思っていることが多いです。
学校を休む罪悪感や不登校でいる自分に嫌悪感を抱き、そのことが大きなストレスになっていることもあります。
また、授業に出席していないことで遅れてしまった勉強を取り返せるかどうか不安に思うケースもあります。
お子さん本人はその状況を深刻にとらえているので、傷つきやすく疲れやすい状態になっています。
子どもの特性や気持ちに寄り添った過ごし方や接し方を考える
お子さんが安心して生活できるよう、それぞれの特性に応じた接し方を心がけましょう。
発達障がいのお子さんはとても繊細なので、学校に行けないお子さんにはしっかりとケアをしてあげることが不可欠です。
学校に通うことで得られるものはたくさんあるかと思いますが、急がないようにしましょう。
不登校児童生徒数が急増している今、だんだんと学校以外の学びの場や活動の場も増えてきています。お子さんのやりたいことや過ごしやすい場所を話し合いながら、フリースクールなどの居場所を検討するのもいいでしょう。
学校に行けない間の過ごし方で気をつけたいこと
発達障がいの有無に限らず、学校に行けなくなったお子さんは、一時的に不登校の状態になっています。心のケガをしているような状態です。
後ろ向きにならず、やりたいことを見つけ前向きに過ごせるように、3つのことに気をつけて過ごし方を見守りましょう。
①何かやりたいことを一緒に探してあげる
家で何もやることがなく、時間を持て余していると、お子さんの心理状態は不健康になっていきます。
「学校に行けてない自分」をネガティブにとらえ、どんどん深刻になってしまうかもしれません。
そうならないように、お子さんが普段やりたいことをしながら楽しく過ごせるように、一緒にやりたいことを探してあげましょう。
お子さんがやりたいことが分からない場合は「ちょっとこれ手伝って」や「こういうの一緒にやりたいんだけど、どうかな?」など誘ってみて、お子さんの反応を見ながら探していきましょう。
②コミュニケーションをたくさんとる
何度も言うように、お子さんは学校に行けてない自分を不安に感じているものです。
好きなことに取り組んだり、前向きに過ごせるようになるには、お子さんの自己肯定感を醸成してあげる必要があります。
お子さんの自己肯定感を醸成するためには、保護者からの承認が大切です。
ちょっとしたことでも「ありがとう」「すごいね」と存在を承認してもらえると、自分に自信が持てるようになってきます。
自分はここに存在していいんだ、好きなことにチャレンジしていいんだ、とお子さんが前向きに過ごせるように、保護者はサポートをしてあげましょう。
③保護者が自分を大切にすること
どうしてもお子さんが学校に行けない状態になると、保護者は悩んだり自分を責めてしまうものです。
ただ、先ほども言ったように不登校は一時的に心をケガしている状態です。
心配しすぎず、のびのび好きなことをさせてあげよう!くらいの心持ちの方が、お子さんにとってもプラスに働くことがあります。
特に発達障がいの特性を持つお子さんは、時に周囲から理解をされなかったり、誤解されてしまうこともあるでしょう。そのことで保護者まで悩ませてしまっていると感じると、より後ろ向きな気持ちが大きくなってしまいます。
お子さんが前向きになるためには、まず保護者が前向きに。保護者自身も自分の気持ちを大切にしながら、穏やかに過ごせるように好きなことや息抜きをするなどしましょう。

発達障がい×不登校の子どもへの接し方のポイント
発達障がいにはさまざまな特性・傾向がありますが「〇〇という傾向があるから、発達障がいだ!」ということではなく、お子さんがどんな特性を持っていて、そのサポートやケアのためにどんなアプローチが有効なのかを理解することが大切です。
不登校のお子さんによく見られる特性と、その特性が見られるお子さんへの接し方のポイントを解説します。
不登校の子に多い発達障がい①ASD:自閉スペクトラム症
ASDの傾向として下記のような特性が挙げられます。
・目で見る情報の方が理解がしやすい
・混乱をしてしまう表現を使ったり、文字通りに受け取ってしまいやすい
・相手の気持ちが読み取りにくい
・部分にとらわれて全体として総合的に考えることが苦手
・予期しない変化はとても苦手
・漠然とした空間、時間の把握が苦手
・金銭感覚が大雑把/異常に厳しい
・自分の気持ちの調整が難しい
・将来のことがイメージしにくい
・決断しにくい(オープンな質問が苦手)
・順序立てて物事を進めるのが苦手
・一度に複数のことを行うのが苦手
【ASDの傾向が見られるお子さんへのアプローチ】
まずは、お子さんが自宅で落ち着いて生活できる環境をつくりましょう。
ものがたくさんある場所や音がたくさん聞こえるような環境では絶えず刺激を受けてしまいます。
静かなスペースを用意したり、壁や机の上がスッキリとしている、物が置かれている場所にはカーテンをつけるなどして気が散らないような環境をつくりましょう。
また、自閉スペクトラム症のお子さんは「いつから」「いつまで」「どこで」「なにを」「どのように」するのかの見通しが立たないことに不安を感じやすいようです。
情報を写真、イラスト、文字、色分けなどを使って「見える化」することで理解を助けて混乱を防ぎ、お子さんが落ち着いて生活や学習に取り組めるようになります。
家庭での環境が整ったら、人との関わり方を教えたり、自分の気持ちの表現の仕方を教えることを家族間で実践していきましょう。
「今日はどんなことをして過ごした?」「予定通りできてどんな気持ち?」など、普段の生活に関することについての会話を増やし、コミュニケーションの幅を広げていきましょう。
不登校の子に多い発達障がい②ADHD:注意欠如・多動症
ADHDの傾向として下記のような特性が挙げられます。
・注意の持続ができない
・うわの空でぼんやりしてしまう
・1つずつのプログラムがきちんと終わらない
・忘れ物、無くしものが多い
・授業中でも立ち歩く
・手足をそわそわ動かす
・しゃべり続けてしまう
・相手の応答を待たずにしゃべる
・順番を待つ、我慢することが苦手
・思ったらすぐ行動に移してしまう
【ADHDの傾向が見られるお子さんへのアプローチ】
ASDのお子さんと同様に、落ち着いた環境づくりは重要です。
自宅では自分のペースで生活ができるように環境を整えましょう。
また、ADHDの特性上、私生活の中で叱られたり、注意を受けやすい傾向にあります。
できないことよりも、できたことや頑張っているところに目を向けて、意識的に褒め、認めてあげる機会をつくりましょう。
成功体験を積むことで、自信がついてやる気につながります。辛抱強く、愛情を示しながら、得意なものにチャレンジできる環境をつくり、得意なことやできることを少しずつ増やせるようサポートしていきましょう。
不登校の子に多い発達障がい③LD:学習障がい
LDの傾向として下記のような特性が挙げられます。
・ことばの遅れが気になる
・勉強についていけない
・集中力、落ち着きがない
・他者との関わりが苦手
・計算や数論が極端に苦手
【LDの傾向が見られるお子さんへのアプローチ】
LDの傾向があるのか、学習が進んでいないのが原因でできていないのか、判断がつきにくく対処しづらいことがあります。
早く気づいてあげることが理想的ですが、どちらにしても保護者の方の対応は一貫して、お子さんの行動を否定せず、根気強くサポートしていく姿勢が重要です。
また、学習方法や教材についてもお子さんにあったものを取り入れ、お子さんの意見を聞きながら試行錯誤していきましょう。
無理に学校の進度に合わせず、自分のペースで勉強ができるようにサポートしてあげてください。
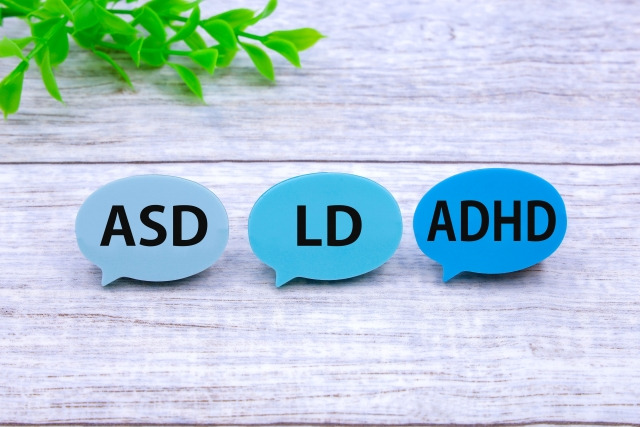
子どもが勉強しない場合の対応
発達障がいで不登校のお子さんが勉強しない場合、無理に勉強を強要するのではなく、お子さんの特性や気持ちに寄り添いながら学びへの意欲を育てていくことが重要です。
具体的な対応方法を解説します。
1. 勉強のハードルを下げる
不登校のお子さんにとって、勉強は大きな負担と感じられることが多いです。最初から完璧を求めず、少しずつ取り組める環境を作りましょう。
たとえば
・1日5分だけ勉強する、1問だけ解くなど、ハードルを極力低く設定
・得意な科目・興味のある分野から取り組む
・ICT教材やゲーム感覚の学習ツールを活用
・自然体験や料理、ものづくりなどの体験型学習を取り入れる
といった方法があります。
「勉強=机に向かって教科書を読むこと」とは限りません。お子さんの興味関心や特性に合わせて、学びのスタイルを工夫しましょう。
2. 勉強に対するプレッシャーを減らす
不登校のお子さんに「勉強しなければならない」と強要すると、余計に拒否感が強まることがあります。焦らず、本人のペースを尊重しましょう。
おすすめなのは、お子さんが勉強しないことを一旦受け入れることです。勉強をしない期間があっても大丈夫です。お子さんの気持ちが安定すれば、自然と学びたい意欲が湧くことがあります。勉強はお子さんの心が整ってからでも遅くありません。
また、声掛けをする際には「勉強しないとダメ」ではなく、「今日は少しだけやってみようか」と前向きに促しましょう。
3. 外部の支援を活用する
家庭だけで抱え込まず、フリースクールや放課後等デイサービス、塾、家庭教師、オンライン学習などの支援機関や学校の力を借りることで、学習のサポートがスムーズに進むことがあります。
学習の形にこだわらず、柔軟に環境を整え、外部のサポートも活用しながら、お子さんのペースを見守っていきましょう。

発達障がいで不登校の子どもの将来・進路
発達障がいを持つお子さんが不登校になると、将来や進路についての保護者の不安は高まりますが、適切なサポートと環境の選択により、お子さんの可能性を最大限に引き出すことができます。
進路の選択肢
◆全日制高校:学力や適性に応じて選択できますが、内申点が影響するため、不登校経験者にはハードルが高い場合もあります。
◆定時制高校:柔軟な時間割で、働きながら通学することも可能です。
◆通信制高校:自宅学習が中心となり、自分のペースで学べます。
◆チャレンジスクール:小・中学校時代に不登校だったお子さんや、高校を中退したお子さんなどを対象とする、自治体が独自に運営する学校です。
◆専門学校への進学:実践的な技術や資格取得を目指す場合に適しています。
◆大学進学:学問を深く学びたい場合や、特定の職業を目指す際の選択肢となります。高校卒業資格が必要ですが、不登校の期間があっても、高卒認定試験を受けるなど柔軟な方法で資格を取得できます。
◆就職:一般企業への就職や、障がい者雇用枠を活用する方法があります。
◆就労準備支援:就労移行支援事業所などで、社会人としてのスキルやマナーを学ぶことができます。
支援のポイント
お子さんの得意・不得意を理解し、それに応じた学習方法や環境を提供することが重要です。
お子さん自身の意志や興味を尊重し、進路選択に主体的に関わらせることで、モチベーションを高めることができます。
また、学校教育だけでなく、フリースクールやオンライン学習など、多様な学びの場を検討することも有効です。
不登校や発達障がいは、お子さんの個性の一部であり、それ自体が将来を閉ざすものではありません。適切な支援と環境のもとで、お子さんの可能性を広げることができます。

学校の先生はどんなフォローをしてくれる?
発達障がいで不登校になったお子さんに対し、学校の先生ができるフォローは多岐にわたります。お子さんの特性や状況に合わせて、以下のようなサポートを行うことが一般的です。
1. 学校復帰に向けたサポート
個別の教育支援計画の作成
学校側が保護者や専門家と連携し、お子さんの特性や状態に合わせた「個別の教育支援計画」を作成します。
学習内容や登校の進め方などを具体的に検討し、段階的な復帰をサポートします。
別室登校の対応
クラスに戻ることが難しい場合、保健室や相談室、空き教室などで学習する「別室登校」が選択されることがあります。お子さんのペースに合わせ、少しずつ環境に慣れる支援です。
短時間・段階的な登校の提案
一日フルに登校するのではなく、朝の会や特定の授業だけ参加するなど、負担の少ない形から登校をスタートします。
2. 学習面のサポート
授業内容の個別対応
発達障がいの特性に応じて、授業内容を個別に調整します。
たとえば、学習障がい(LD)を持つお子さんには読み書きのサポート、ADHDのお子さんには集中しやすい学習環境を提供することがあります。
ICT機器の活用
タブレットやパソコンを使って学習することで、学びやすさを向上させる工夫が行われることもあります。特に視覚的に理解しやすい教材は効果的です。
在宅学習のサポート
学校に行けない間、自宅で学習を進められるように宿題や教材を届けたり、オンラインで授業を提供することもあります。
3. 生活面・メンタル面のサポート
カウンセリングや相談対応
学校のスクールカウンセラーや特別支援コーディネーターが、お子さんや保護者に対して心理的なサポートを行います。
悩みや不安を聞き取りながら、お子さん自身の気持ちに寄り添います。
交流の機会づくり
学校の先生がお子さんに対して、同年代の友達と少しずつ交流できる場を設けることがあります。
たとえば、休み時間の短い会話や、グループ学習の機会を提案します。
4. 外部機関との連携
学校だけでは対応が難しい場合、先生が発達障がい支援センターや教育相談所など、専門機関への相談や連携を提案することがあります。
また、必要に応じて通級指導教室や特別支援学級への移行も検討されることがあります。

発達障がいで不登校の子どもの支援事例
発達障がいで不登校のお子さんに対する支援事例は多様で、お子さんの特性や家庭の状況に合わせた柔軟なアプローチが求められます。
具体的な支援事例をいくつか紹介します。
1. 学校と連携した段階的な登校支援
事例① 小学校5年生・ADHD(注意欠陥・多動性障がい)
状況:教室の騒がしさや集団生活に馴染めず、不安から登校を拒否するように。
支援内容:学校と保護者が連携し、短時間の別室登校からスタート。担任の先生が1対1で学習サポートを行い、少しずつ友達と交流する機会を設ける。学校の特別支援コーディネーターと相談し、本人の得意分野を活かした授業を提案。
結果:本人の負担が減り、週に数回登校できるようになり、安心感が生まれた。
2. 通級指導教室(特別支援)を活用した学習支援
事例②:中学1年生・ASD(自閉スペクトラム症)
状況:集団行動が苦手で、クラスメイトとのコミュニケーションがうまく取れず、登校しなくなった。
支援内容:通級指導教室で、コミュニケーションスキルや対人関係を学ぶプログラムを受講。学習の遅れを取り戻すため、ICT(タブレット)を活用した個別学習を実施。学校カウンセラーが本人と定期的に面談し、不安や悩みを共有。
結果:少しずつ対人スキルが向上し、通級を通して友人関係も築けるようになった。
3. フリースクールとの併用で学びの場を確保
事例③:高校1年生・学習障がい(LD)
状況:読み書きの困難が原因で授業についていけず、自信を喪失して不登校に。
支援内容:学校と並行してフリースクールに通い、個別指導で学習をサポート。得意な分野(プログラミングや芸術)を伸ばす活動を取り入れ、自信を回復。学校の担任とフリースクールが連携し、出席日数の扱いや単位認定を調整。
結果:自分のペースで学ぶことで学習意欲が戻り、将来の進路に向けた目標を見つけた。
4. 専門機関との連携で家庭サポート
事例④:小学校3年生・発達性協調運動障がい(DCD)
状況:体育や工作などの活動が苦手で自信を失い、不登校に。
支援内容:学校が発達障がい支援センターと連携し、運動や生活スキルを向上させるための支援を受ける。家庭では作業療法士(OT)の指導を受け、日常生活動作(ADL)の訓練を実施。学校では担任が得意な学習分野を見つけ、成功体験を増やす取り組みを行う。
結果:運動への苦手意識が和らぎ、少しずつ登校への意欲が戻ってきた。
5. オンライン学習の導入で自宅学習を支援
事例⑤:中学3年生・ADHDと不安障がい
状況:教室の環境や対人関係に強いストレスを感じ、不登校に。
支援内容:学校と話し合い、オンライン学習を導入。自宅でリアルタイムの授業を受けられるようにする。専門機関と連携し、不安障がいに対するカウンセリングを継続的に実施。保護者もサポートを受け、家庭での接し方や声かけについて学ぶ。
結果:自宅で学びを継続できたことで学力の遅れを防ぎ、本人の安心感も高まった。
支援のポイントまとめ
発達障がいのお子さんに対する支援事例はさまざまですが、重要なのはお子さんの気持ちに寄り添いながら、一歩ずつ進んでいくことです。
学校や専門機関、家庭が連携することで、お子さんの成長を支える道が開けます。
ツナグバは専門の臨床心理士の監修のもと、皆様のお悩みを相談できるQ&A機能があります。専門家の意見を聞いたり、同じ悩みを持つ人と交流することで、気持ちが軽くなるかもしれません。
無料会員登録をして、ぜひツナグバを一つの居場所にしてみてくださいね。
▶無料会員登録はコチラから
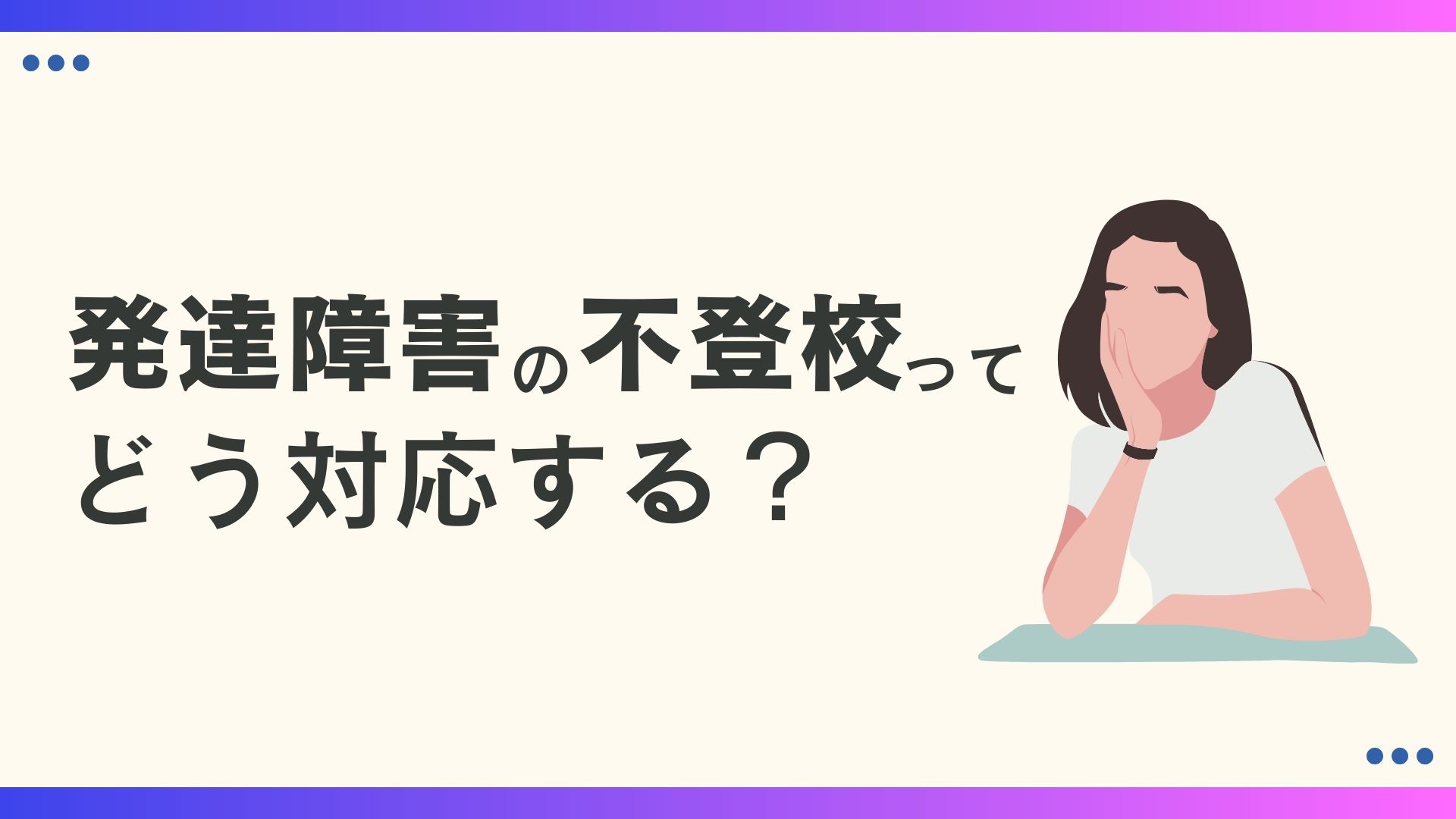

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る