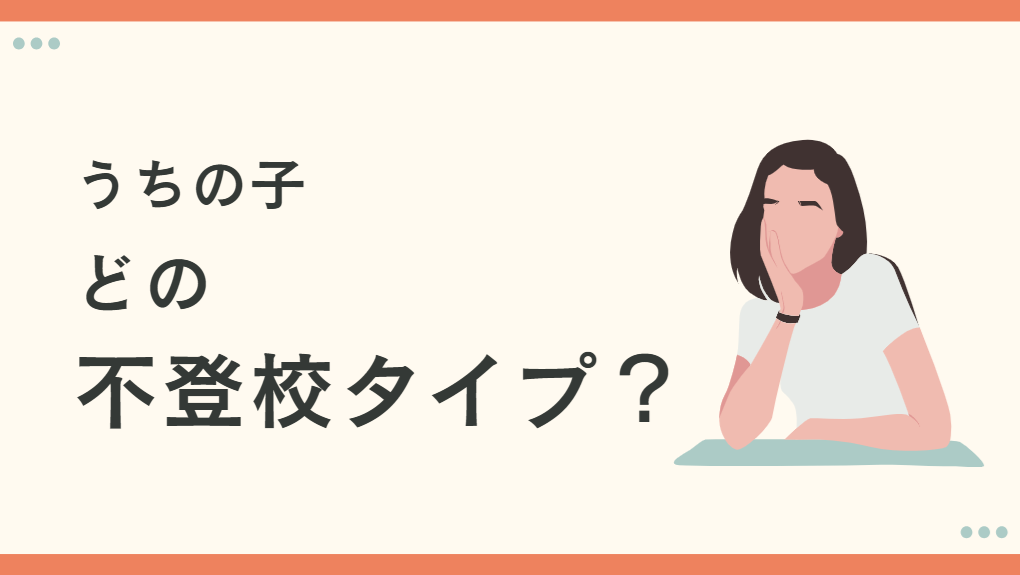お子さんが学校に行けなくなったら、保護者は「いつになったら戻れるのだろう」「このままずっと不登校だったらどうしよう」と不安や焦りを感じるものです。
しかし、不登校は「終わり」ではありません。お子さんが立ち止まり、自分のリズムを取り戻すための大切な時間でもあるのです。
復帰と一口に言っても、そこに至るまでの道のりはお子さんによってまったく異なります。すぐに戻れるお子さんもいれば、何度かチャレンジしながら少しずつ前進するお子さんもいます。あるいは、学校以外の場で自分らしく成長していくお子さんもいるでしょう。
本記事では、そんな不登校からの復帰について、
■実際の復帰率やその現実
■お子さんの心の変化や兆し
■家庭でできる対応や段階的な復帰のステップ
■再び不登校になったときの考え方
■勉強や社会とのつながりの取り戻し方
■保護者としてのサポートのあり方
を、段階ごとにわかりやすく解説していきます。
不登校からの「復帰」は、お子さんの人生のなかでひとつの分岐点。大切なのは、本人のペースで、自分らしく前を向いて進める環境をつくること。
あきらめないで、一歩ずつ。
お子さんと一緒に歩む保護者にとって、このガイドが少しでも心の支えとなることを願っています。
不登校からの復帰率は?数字で見る現実と希望
不登校からの「復帰」と聞くと、保護者としては「どれくらいの割合が戻れているのか?」というデータが気になるものです。
しかし、復帰率の数字だけを見て一喜一憂するのではなく、その背景や意味を知ることが大切です。
ここでは文部科学省の統計をもとに、実際の復帰率とともに、「復帰」の本当の意味についても考えていきましょう。
文科省等のデータに基づいた復帰率(小中別)
文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校調査」によると、令和4年度の不登校の児童生徒数は以下のように報告されています。
小学生:約10万人(約1.4%)
中学生:約20万人(約6
そのうち、「一定期間登校が回復した」とされる割合(いわゆる復帰率)は、小学生で約45%、中学生では約35%程度という報告もあります。
ただし、この「復帰」は必ずしも完全な登校再開を意味するわけではなく、一時的な登校や部分登校、フリースクールなど他の学びの場への参加も含まれます。
数字はあくまで「目安」であり、お子さんの状況や受け入れ環境によって道のりはさまざまだということを前提に見ていく必要があります。
「復帰=学校に戻る」だけではない、多様な選択肢
「復帰」というと、多くの人が「元の学校に毎日通うこと」をイメージするかもしれません。
しかし、近年は「学びの場」や「社会との接点」も多様化しており、
■フリースクールや適応指導教室に通う
■オンラインでの学習に切り替える
■通信制高校や高卒認定試験を目指す
■地域の活動やボランティアに参加する
など、本人にとって安心して過ごせる場所に戻る=復帰と捉える動きが広がっています。
つまり、「学校に戻らないと復帰ではない」という考えにとらわれる必要はありません。
お子さんが再び何かに向かって歩み始めたとき、それが復帰の第一歩です。
一度戻ってもまた休むケースも多い:継続より“安定”が大切
実は、不登校から一度学校に戻ったとしても、再び不登校になるケースは少なくありません。
これを「失敗」と捉えてしまうと、お子さん自身も保護者も深く落ち込んでしまいがちです。それは失敗ではなく、お子さんが今の環境にまだエネルギー的に合っていないだけのこと。
大切なのは、「連続して登校できているか」ではなく、
お子さんが安心して、自分のペースで過ごせているかどうかです。
学校に戻ることも、戻らないことも、お子さんにとって必要な選択のひとつ。
親ができるのは、「子どものリズムを信じて見守ること」だといえるでしょう。
復帰できる兆しとは?子どもの変化に気づくサイン
不登校のお子さんが再び前を向き始めるとき、そこには必ず小さな変化の兆しがあります。「復帰しよう」と自分で言葉にする前に、生活や態度に少しずつ前向きな動きが見え始めるのです。
ここでは、不登校からの復帰のきっかけとなるサインについて具体的に紹介します。
保護者が気づき、見守ることが、お子さん自身の自信や行動意欲につながっていきます。
■規則正しい生活に戻ろうとする
■起床・就寝のリズムが整い始める
■食事の時間や内容に気を使うようになる
■入浴や身だしなみを自分で整えるようになる
これらは、心と体に少しずつエネルギーが戻ってきた証拠です。
生活リズムの回復は、心の安定にも直結します。
■学校の話題を自分から出すようになる
■「友達はどうしてるかな」「〇〇先生は元気かな」など、学校に関する発言が増える
■学校の行事や授業について関心を持ち始める
■過去の出来事について語るようになる
これは、心の中で「学校」との距離が少し縮まりつつある証です。
無理に話を広げず、お子さんのペースで耳を傾ける姿勢が大切です。
■外に出る・誰かと関わりたがるようになる
■買い物や散歩など、外出を前向きにとらえるようになる
■家族以外の人(友人・親戚など)と会いたがる
■SNSなどで他者とつながろうとする
閉じこもっていた時間を抜け出し、外の世界への興味や関心が芽生え始めたサインです。
この時期は、「一緒に行こうか」と声をかけるなど、そっと背中を押してあげましょう。
■「勉強しようかな」と言い出すなど、意欲の復活
■自分から教科書を開く、問題集をやり始める
■パソコンやタブレットで学習系の動画を見る
■「勉強しないと…」というつぶやきが増える
これは復帰への大きなサインです。
ただし、「じゃあ毎日やろう!」と急かすのは逆効果。
ほんの5分でも「やろうとしたこと自体」を肯定してあげるのが何よりのサポートです。
兆しに気づいたら、焦らず「見守る」ことが一番の支援
こうした兆しが見え始めたら、復帰はすでに“始まっている”と言っていいでしょう。
ただし、焦って先に進ませようとすると、せっかく育ち始めた意欲の芽を摘んでしまうこともあります。
「やろうとしている」「気になっている」「少し外を見ようとしている」——
そんなお子さんの気持ちを尊重しながら、寄り添い、信じて待つことが何より大切です。
不登校から復帰するまでのステップと心構え
不登校からの復帰には、明確な「正解」や「ルート」はありません。
ただ、多くのお子さんがたどる共通の段階や心の流れがあります。それを知っておくことで、焦らずに寄り添うことができるでしょう。
ここでは、子どもが「もう一度、動き出そう」と思えるまでの流れと、保護者にできる関わり方を5つのステップに分けてご紹介します。
① 休息と安心のフェーズ
まず大切なのは、「もう頑張らなくていい」と心と体を休ませる時間です。
・朝起きられない
・無気力で何もしたがらない
・イライラしたり、言葉が荒くなる
といった状態は、エネルギーが切れているサイン。無理に外に出そうとせず、安心できる環境でただ「一緒にいる」ことを大切にしましょう。
✦ 心構え:「まず休むことが必要」と本人も周囲にも認める
② 家庭内での生活リズム回復
少しずつエネルギーが戻ってくると、「生活のリズム」が整い始めます。
・夜型から昼型の生活に戻り始める
・食事や身だしなみを気にするようになる
・会話が増え、感情が表現されてくる
この段階では、「〇時に起きよう」「一緒にご飯を食べよう」といった日常の小さな約束が回復へのきっかけになります。
✦ 心構え:ルールより“会話”を大切に。小さな成功を喜ぶ
③ 外の世界との接点を少しずつ
次に大事なのは、「家の外」や「他人」との接点を取り戻すこと。
・散歩や買い物に付き添って出かける
・フリースクールや居場所支援への参加を検討する
・オンラインで安心できるコミュニティとつながる
いきなり学校に戻るのではなく、本人が「怖くない」と思える小さな一歩からスタートするのがコツです。
✦ 心構え:「外とつながれた」こと自体を大きく評価する
④ 学びの再開(家庭学習、個別支援など)
外の刺激に少し慣れてきたら、学びを再開するタイミングです。
・家庭でのドリルや動画視聴など、無理のない学習から
・個別指導、オンライン家庭教師などの検討
・興味のある分野からスタートするのもOK
ここで大切なのは、「勉強=学校のペースに追いつくこと」ではないと伝えること。
本人の「やってみたい」という気持ちを尊重してあげましょう。
✦ 心構え:学びの目的は「追いつくこと」より「自信を取り戻すこと」
⑤ 学校・社会への段階的な接続
最終的に、学校への復帰や、社会とのつながりに向けて動き出すお子さんもいます。
・別室登校・保健室登校・午後から登校など、柔軟な対応
・フリースクールや通信制高校への進学も選択肢
・学校に戻らず、地域や社会とつながっていく道もある
どんな道を選んでも、「本人が安心できる環境」であることが第一です。
「完全復帰」をゴールにせず、「いま、その子に合った場所に戻る」ことを大切にしてください。
✦ 心構え:復帰は“通過点”。お子さんの納得感が何より大事
このように、不登校からの復帰は「階段」ではなく「ゆるやかな坂道」のようなもの。
時に立ち止まりながらも、一歩ずつ確かに前に進んでいることを信じて、伴走していきましょう。
復帰したけどまた休んでしまう…どう受け止める?
不登校のお子さんが「学校に行ってみよう」と思い、実際に登校できたとき、多くの保護者は胸をなでおろすでしょう。ところが、数日、あるいは数週間後に「また行けなくなった」となったとき、「元に戻ってしまった」「やっぱりダメだったのでは…」と落胆し、戸惑うことも少なくありません。
しかし、復帰後に再び休むことは、決して珍しいことではありません。
むしろ、不登校を経験したお子さんの多くが「行けた」と「行けない」を行き来しながら、自分のペースを見つけていくのです。ここでは、そんな“揺れ戻し”の時期に、どのような視点でお子さんに関わればよいのかを解説します。
復帰→再び不登校は「よくあること」
不登校の回復は、一直線に改善するものではありません。
「今日は行けた!」という日があっても、そのあとに疲れが出て行けなくなったり、クラスでの小さな出来事が引き金になって後退してしまったりすることは、よくあることです。
でもそれは、「前に進んでいなかった」のではなく、
お子さんなりにチャレンジした結果、気づきや調整が必要だと感じたというサインでもあるのです。
むしろ大切なのは、「一度行けた」という経験を本人がどう受け止め、次にどう向き合うかです。保護者や周囲が「またダメだった」と落ち込んでしまうと、お子さんは余計に自己否定感を抱いてしまいます。
再びの休みは“失敗”ではない
再び学校を休むようになったとき、多くのお子さんは自分を責めています。
「また途中でやめてしまった」「やっぱり自分はだめだ」といった思いが渦巻き、自己肯定感が下がってしまいがちです。
このとき、保護者が伝えたいのは「戻ったことを否定しない」言葉です。
「一回行けたことがすごいよ」
「今日は休むって、自分で決められたんだね」
「また元気が出たら一緒に考えよう」
こうした言葉は、子どもの「挑戦」を認め、「休むこと=悪いことではない」と伝える安心感を生みます。
回復の道のりには、必ず波があります。
その波を共に乗り越えていく存在であることが、保護者にできる大きな支援です。
本人のエネルギーや環境調整のタイミングを見直す
再びの不登校には、いくつかの背景があることが多いです。
たとえば、
・学校の人間関係にまだ不安がある
・登校することに集中力や体力が追いつかない
・周囲の「行けるなら行って当然」という空気にプレッシャーを感じた
というような場合は、「なぜまた休んだのか」を無理に聞き出すのではなく、お子さんの状態や環境を一緒に見直すことが重要です。
・週1回の登校にする
・午前中だけにする
・学校ではなくフリースクールに通う
・オンラインでつながる選択肢を増やす
など、“全部頑張る”ではなく、“自分が無理なくできる形”を選べるようにサポートすることが、次のチャレンジへの前向きな足がかりになります。
「また休んでしまった」は、「また自分と向き合い直すチャンスが来た」ということ。
そんなふうにとらえ直すことで、保護者も子どもも、気持ちが少し軽くなるかもしれません。
不登校からの「勉強の復帰」どう進める?
不登校のお子さんが少しずつ元気を取り戻してくると、次に気になるのが「勉強の遅れ」ではないでしょうか。保護者の多くは「学校に戻るためには、まず勉強を取り戻さなければ」と焦る気持ちを抱えています。しかし、勉強の復帰も、心の回復と同じように“本人のペース”が何より大切です。
ここでは、無理なく、でも確実に学びに戻っていくための考え方と具体的なステップを紹介します。
いきなり追いつこうとしないこと
まず大切なのは、「みんなに追いつかなければ」と思い込まないこと。
学校の進度に合わせようとすると、お子さんも保護者もプレッシャーを感じやすくなります。
実際には、「全教科完璧にやり直す」必要はありません。
お子さんが「わかる・できる」と思えるところから始めるほうが、意欲も継続しやすいのです。
【ポイント】
・苦手科目は避け、好きな科目から
・「1日1問」など、達成しやすい目標を設定
・他人と比べず、「昨日の自分」との比較を大事にする
わかるところから、自信をつける学習方法
勉強の再開は、自己肯定感の回復と密接に関わっています。
「これならできた」「ちょっと楽しいかも」と思える体験を積み重ねることが、再び学ぶ力を育てます。
【具体的な方法】
・学年をさかのぼって、簡単なドリルや動画教材からスタート
・解けた問題に〇をつけて「見える達成感」を作る
・「1日5分」「1日1ページ」など超・短時間設定
特に漢字・計算・英単語などは、少しずつ進めるだけでも実感が得られやすい分野です。
家庭学習→個別指導・オンライン塾など選択肢紹介
お子さんによっては、自宅での勉強が合わない場合もあります。そんなときは、外部の力を借りることをためらわないでください。
【選択肢の例】
・オンライン学習サービス
・スタディサプリ・すらら・NHK for Schoolなど、映像で自分のペースで学べるツールが充実
・家庭教師・オンライン個別指導
マンツーマンで丁寧にサポート。不登校専門の対応が可能なサービスも増えています。
・フリースクール・地域の学習支援拠点
勉強と居場所の両方を提供。人とのつながりが苦手な子も徐々に慣れていける環境。
勉強の復帰は、学力だけでなく、自信と安心感を取り戻すプロセスです。
大切なのは、たとえ一歩でも「自分で前に進めた」という実感を持てること。
焦らず、比べず、お子さんのタイミングを尊重しながら、寄り添って進めていきましょう。
学校だけじゃない!広がる「社会復帰」の選択肢
今の時代は、学校以外にも学び、成長し、社会とつながる多様な選択肢があります。ここでは、不登校のお子さんにとっての「社会復帰」のあり方についてご紹介します。
高卒認定、通信制高校、専門学校、就労支援など
不登校が長引いた場合でも、中学校卒業後の進路は一つではありません。
通信制高校
自宅中心の学習+スクーリング(登校日は少なめ)。自分のペースで学習を進められるため、不登校経験者にとって現実的な選択肢。
高卒認定試験(旧大検)
高校に通わずに、高校卒業と同等の学力を証明できる国家試験。合格すれば大学受験も可能に。
専門学校や職業訓練校
高校卒業後、自分の興味ある分野(美容、IT、調理、デザインなど)に特化した学びができ、実践的なスキル習得を目指せる。
就労支援・若者サポートステーション
高校卒業後、すぐに就職を考える場合は、社会に出る準備を支援する機関や団体も多数存在。社会参加へのステップとして活用されている。
フリースクールや地域の居場所支援
中学生の間に「完全な復帰」は難しいと感じる場合でも、社会と少しずつつながる手段はあります。
フリースクール
学校以外の安心できる学びの場。個々のペースを尊重しながら、勉強や人とのつながりを取り戻す環境を提供しています。
適応指導教室(教育支援センター)
教育委員会が設置。部分的な通所や学習支援、学校への橋渡し的役割を果たす。
NPOや市民団体による“子どもの居場所”
ボードゲーム・読書・料理など、活動を通してお子さんが無理なく集える場所も増えています。
社会復帰=社会との再接続。学校に戻らなくてもよい
「学校に戻らなければ社会復帰できない」という考え方は、もはや過去のものです。
むしろ、学校に戻らずとも、“自分なりの社会とのつながり方”を見つけられることが、今の時代に合った回復の形です。
たとえば、
・自宅でイラストを描き、SNSで発信してつながりが生まれる
・ボランティア活動を通して他者との関係性を築く
・小さなアルバイトや地域活動に関わってみる
といった活動を通して「人と関わることが怖くない」「何かに参加できる」という実感があれば、それも立派な社会復帰の一歩です。
お子さんが学校に戻れないことに悩むのではなく、「どんな形で社会と関われるか」を一緒に探していく姿勢が、これからの支援には必要です。
保護者ができる最大のサポートとは?
不登校のお子さんを支える中で、保護者自身が「自分はどう関わればいいのか」と悩む場面は多いでしょう。ときには無力感や焦りを感じることもあるかもしれません。
けれど、子どもが安心して回復していくために、保護者の存在は何よりの支えになります。
ここでは、不登校からの回復と復帰を目指すうえで、保護者が意識したいサポートのポイントをまとめました。
焦らない・比べない
「いつになったら学校に戻れるの?」「みんなは普通に通っているのに…」
そんな気持ちが頭をよぎることは自然なことです。ですが、焦りや比較はお子さんにとって大きなプレッシャーになります。
大切なのは、「今の状態でも大丈夫」「あなたはあなたのペースでいいんだよ」というメッセージを日常的に伝えること。
言葉に出さなくても、表情や態度から子どもはその安心感を感じ取っています。
子どもが「戻りたい」と思える環境づくり
無理に登校させるのではなく、「戻ってみたいな」と思えるきっかけや雰囲気を整えることが、保護者の大切な役割です。
■生活リズムを整える
■学校の話題は出しすぎず、否定もせずに聞く
■小さな前進を見逃さずに喜ぶ
■家の中に安心できる居場所・時間をつくる
お子さんは「挑戦しても受け止めてもらえる」と思えたときに、自然と一歩を踏み出します。
専門機関・支援団体への相談も視野に
保護者だけで抱え込まないことも、とても大切です。
お子さんの状況に応じて、以下のような外部の力を借りることを前向きに検討してみましょう。
■スクールカウンセラーや教育相談センター
■フリースクールや居場所支援団体
■精神科や児童思春期外来などの専門医療機関
■保護者のための相談会や当事者会
不登校は、決して「家庭だけの問題」ではありません。
「頼っていい相手がいる」という安心感が、保護者にもお子さんにも必要なのです。
できたことを具体的に褒める
自信を失いがちなお子さんにとって、「できたことを認めてもらえる経験」は何よりも大きな力になります。
「朝起きられたね」
「ご飯ちゃんと食べられたね」
「ちょっと外に出られたの、すごいよ」
こうした小さなことでも、「できた自分」を感じる体験が、次の一歩につながっていきます。
完璧を求めすぎない
「ちゃんとした親でいなければ」「いいサポートをしなければ」と、自分に厳しくなりすぎると、保護者自身も疲れてしまいます。
うまく言葉にできなかった日も、イライラしてしまった日も、お子さんにとっては“そばにいる”こと自体が支えです。
完璧じゃなくていい。時にはお子さんに「今日ちょっと疲れてるんだ」と伝えてもいい。
大事なのは、完璧な対応よりも“つながりを持ち続けること”です。
お子さんが前を向こうとする瞬間を、焦らず、信じて、待つ。
保護者のその姿勢が、なによりも力強い支えになります。
まとめ:復帰は「目的」ではなく「選択肢のひとつ」。本人のペースを尊重して
不登校になると、どうしても「学校に戻ること」がゴールのように思えてしまいます。
しかし、この記事を通して見えてきたのは、復帰は“目的”ではなく、“数ある選択肢のひとつ”だということです。
お子さんが学校に行けなくなる背景には、心の疲れ、対人関係、環境要因、発達特性など、さまざまな理由があります。そしてそれは、努力や根性だけではどうにもならない問題であることが多いのです。
だからこそ大切なのは、「戻ること」にこだわるよりも、「お子さんが自分らしくいられる場所を一緒に探す」こと。
その中で、本人のタイミングで「戻ってみたい」と感じる瞬間が来るかもしれないし、別の道に進むという選択をするかもしれません。どちらであっても、それは立派な前進です。
最後に、覚えておいてほしいのは、「学校に行けているから安心」ではなく、お子さんが“安心して生きられているか”が、本当の安心だということ。
どうか焦らず、比べず、お子さんの歩幅で歩んでください。
回り道に見えるその時間が、実は大きな力を育てていることに、きっと後で気づくはずです。
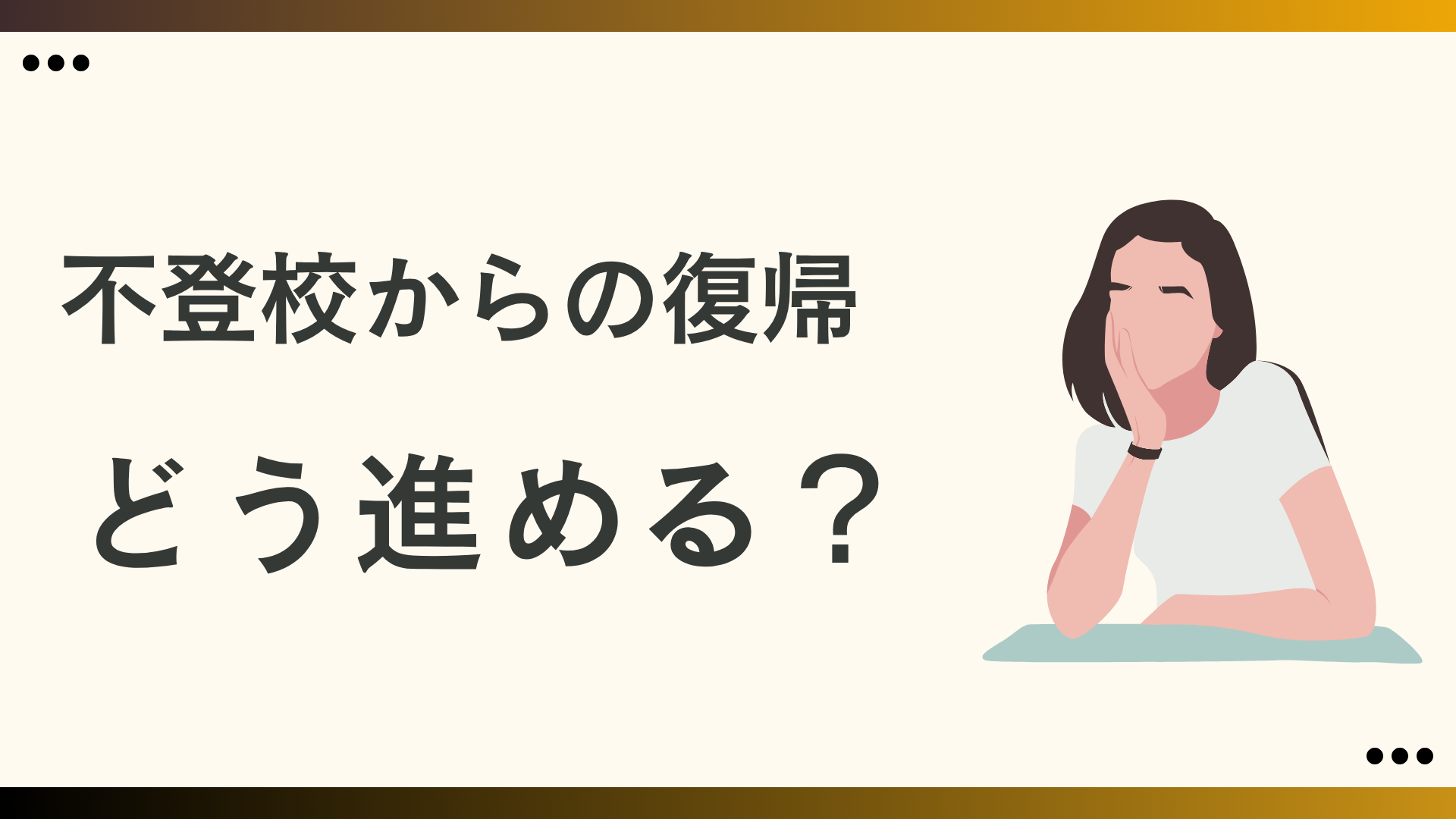

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る