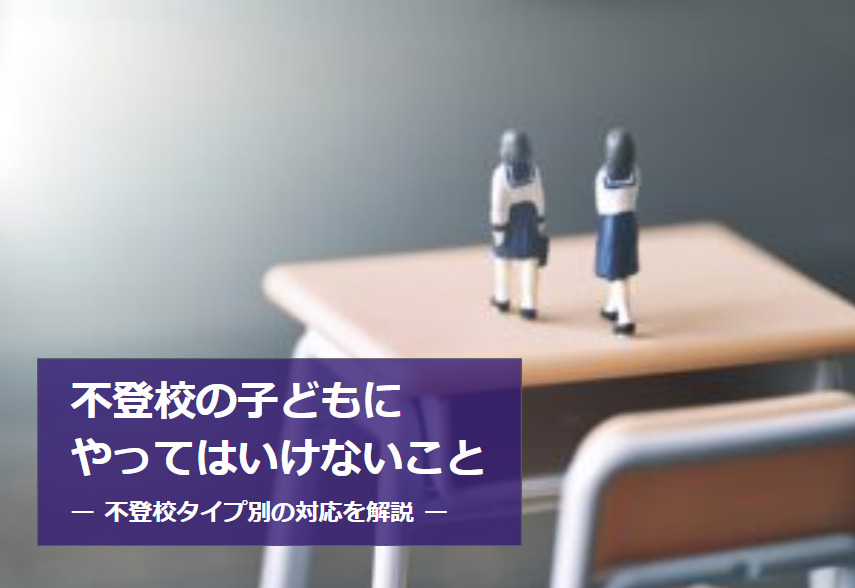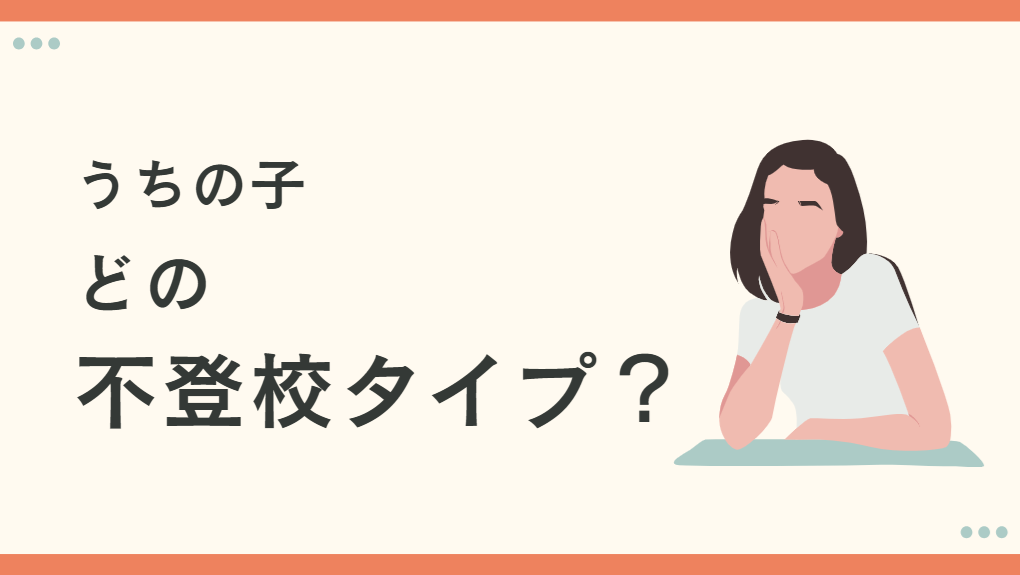「月曜日になると、急にお腹が痛くなる」
「前の晩までは元気だったのに、朝になると行けない」
お子さんにそんな日が増えてきた…。
ある日は登校できて、ある日は玄関で固まってしまう。元気そうに見えても、気持ちは不安定。「また今日も行けないかもしれない」と、保護者も毎朝ハラハラしてしまう…。
そんな状況に悩んでいる場合、もしかすると「五月雨登校(さみだれとうこう)」のサインかもしれません。
「五月雨登校」とは、学校に“行ったり行かなかったり”を繰り返す登校のかたちのこと。完全な不登校とは異なり、「行ける日もある」という状態が続くのが特徴です。
特に中学生や小学生のお子さんに多く見られ、保護者の方が戸惑いや不安を抱えることも少なくありません。
「いつまでこの状態が続くの?」「無理にでも毎日行かせた方がいいの?」と、悩んでいませんか?
この記事では、そんな「五月雨登校」の特徴や原因、長引いたときの考え方、そして具体的な対処法までを、わかりやすく解説します。
「五月雨登校」とは?中学生・小学生に多い“ゆらぎ”のある登校
不登校とは違う?「行ける日もある」のが特徴
「五月雨登校」とは、登校したり休んだりを繰り返す状態のことです。完全な不登校と違い、「学校に行ける日もある」というのが大きな特徴です。
たとえば、
・月曜日は休んだけど火曜日は行けた
・朝はしんどかったけど、2時間目から行けた
・保健室登校や別室登校ならできる日もある
といったように、日によって登校のパターンに“ゆらぎ”がある状態を指します。
このような登校のゆれは、小学生・中学生の成長過程においては珍しくありません。ですが、周囲と同じように「毎日通うのが当たり前」と考えていると、「何が問題なんだろう」「甘えなのかな」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、「行ける日もある」というのは、お子さんが自分なりに頑張っている証拠でもあります。
「五月雨登校」はなぜ起きる?|主な原因
五月雨登校にはさまざまな背景やきっかけがあります。ここではよく見られる原因をいくつか紹介します。
■ 学校への不安・人間関係のストレス
・苦手なクラスメイトがいる
・担任の先生と合わない
・授業についていけない、発表が苦手
・部活動や友人関係での悩み
こうした不安やストレスが積み重なると、学校に行くことそのものが心理的負担となり、登校が不安定になります。
■ 疲れやすさ・HSP傾向(感受性が強い)
音や人混みに敏感だったり、緊張しやすかったりといった繊細な気質(HSP)を持つお子さんは、学校という刺激の多い環境に疲れてしまうことがあります。
本人にとっては、「通う」「人と関わる」というだけでエネルギーを使い果たしてしまうことがあるのです。
■ 週明け(月曜)に多いのはなぜ?
「月曜日だけいつも行けない」「週末明けが一番しんどい」という声もよく聞かれます。
これは、週末に気が緩み、安心できる家庭で過ごすことで、学校との落差がより大きく感じられるためです。また、月曜日に提出物やテスト、朝会など「特別なプレッシャー」がある学校も多く、“月曜日だけ不調”はよくある現象でもあります。
「行ったり行かなかったり」は、お子さんの中での葛藤の現れです。
「完全に拒否しているわけではない」という点に目を向けることで、次の一歩に繋がるヒントが見えてくるかもしれません。
五月雨登校の状態が「長引く」…どう受け止めればいい?
「そのうち落ち着いて毎日行けるようになるはず」と思っていたのに、1か月、3か月、半年と、行けたり行けなかったりの状態が続くと、保護者としては「これってもう不登校なの?」「このままで大丈夫?」と不安になるものです。
ですが、五月雨登校は“経過の一つ”として自然な状態であることも多いです。
無理に「毎日通わせよう」とする前に、まずは今の状態の受け止め方を見直してみることが、回復の第一歩になるかもしれません。
無理に「完全登校」を目指さなくていい理由
多くの保護者は、「元のように毎日学校に行ける状態に戻したい」と思うでしょう。
しかし、お子さんにとっては“毎日登校”が今の自分に合っていない可能性もあります。
大切なのは、「今の本人が無理なくできる範囲」をベースにして、小さな安定を積み重ねていくこと。
完全登校をゴールにしてしまうと、途中でつまずいたときに「やっぱりダメだった」と感じてしまい、かえって自信や意欲を失うこともあります。
保護者の焦りがお子さんに伝わることも
「どうして今日は行けないの?」「もう何日休んでると思ってるの?」
そんな言葉がつい口をついて出てしまうこと、ありませんか?
保護者が焦る気持ちはよくわかります。でも、その焦りや不安は子どもにも敏感に伝わります。
お子さんは「お母さんを困らせてる」「申し訳ない」という罪悪感を抱えていることも多く、さらに身動きが取れなくなることもあります。
まずは、「今の状態で大丈夫」と親が安心して見守ることで、子ども自身の中にも落ち着きが生まれます。
「行けた日」を肯定的に見る視点
不登校傾向になると、「行けない日」にばかり目が向きがちです。
しかし、「行けた日」こそ、お子さん本人にとっては大きなチャレンジだったはず。
・朝起きられた
・制服に着替えた
・玄関まで出られた
・1時間目だけでも出席できた
こうした小さな“できた”を家族で一緒に喜ぶことが、次へのエネルギーになります。
「今日は無理だった」と落ち込むよりも、「昨日は行けたね」「また行ける日があるといいね」と、“揺らぎ”を肯定する視点を持っていくことが大切です。
お子さんの状態は、波のように揺れながら少しずつ前に進んでいます。
保護者がその“揺らぎ”を認めて受け止めることが、お子さんにとって何よりの安心になります。
「五月雨登校」への具体的な対処法とは?
お子さんが「行ったり行かなかったり」の状態にあるとき、保護者として「どう対応するのが正解なんだろう?」と迷うことも多いでしょう。
ここでは、五月雨登校のお子さんに向き合う際に心がけたい具体的な対処法をご紹介します。
大切なのは、“登校させること”を目的にするのではなく、「今の子どもの気持ちに寄り添う」ことを第一にする姿勢です。
対処法① 「行かせようとする」より「話を聴く」
「今日こそは行けるよね?」と無理に背中を押したくなることもあるかもしれません。
しかし、登校を促す前に、まずはお子さんの話を丁寧に聴くことが何より大切です。
・「どうして休みたいの?」ではなく、「今、どんな気持ち?」と聴く
・否定せず、途中で口をはさまず、うなずいて聴く
・話せない場合は、絵やメモなど他の手段もOK
「お母さんになら(お父さんになら)話しても大丈夫」と思える安心感が、徐々に自己理解や回復につながっていきます。
「月曜だけ休みたい」など希望のパターンを尊重
「月曜日だけ休みたい」「午前中だけ行きたい」「保健室で過ごしたい」など、お子さんが自分から出してくる“希望のパターン”は、自分の状態をコントロールしようとするサインです。
そのような希望が出たら、頭ごなしに否定せず、できる限り尊重してあげましょう。
パターンが定まることでお子さん自身も安心し、「それなら頑張ってみようかな」と思えることがあります。
「休んでもいい場所」があると安心する
「学校はしんどい、でも家にずっといるのも不安」
そんなお子さんにとって、“休んでも行ける場所”の存在は非常に大きな支えになります。
たとえば、
・学校内の別室登校(支援室など)
・フリースクールや適応指導教室
・自宅でのオンライン学習や家庭教師
など、学校以外の学びや過ごし方を選択肢として持つことが、お子さんの安心や回復のきっかけになることもあります。
“普通の登校”にこだわらず、「今のお子さんに合う場所」を一緒に探していく姿勢が大切です。
支援や相談先の活用も検討を
五月雨登校が長引くと、家庭だけで抱えきれず、保護者もお子さんも疲弊してしまうことがあります。
そんなときは、外部の支援機関や専門家に相談することも選択肢のひとつです。
教育相談センター・スクールカウンセラー
各自治体には、教育委員会が設置している「教育相談センター」があります。
学校に直接言いづらい悩みも、ここなら客観的な視点で相談に乗ってもらえます。
また、多くの小中学校にはスクールカウンセラーが配置されています。
「相談=登校を強制されるのでは?」と不安になる方もいるかもしれませんが、話を聴くことがメインの役割なので、安心して利用できます。
フリースクール・オンライン学習
「学校以外の場所で学びたい」「安心できる環境で過ごしたい」というお子さんにとって、フリースクールやオンライン学習は強い味方になります。
フリースクールは、勉強だけでなく人との関わりや自分らしさを大切にできる場所です。週に数回だけ通うスタイルや、好きな時間に参加できる自由度の高さも魅力です。
また、オンライン学習は「家から出られない」「人と直接関わるのが不安」といったお子さんにも合う学びの形。
最近では不登校支援に特化したオンライン塾や家庭教師サービスも増えています。
「学校以外の学び」を視野に入れてもいい
「学校に行くこと」がすべてではありません。
文部科学省も、不登校のお子さんに対しては「多様な学びの場の存在を認め、本人の意思を尊重すること」が大切だとしています。
登校以外にも、家庭学習・地域の活動・フリースクール・オンラインなど、お子さんが自分らしく学べる場所を見つけることが、将来的な自立や社会とのつながりにもつながります。
お子さんの今の姿に合ったサポートを取り入れることは、保護者にとっても安心できる環境づくりの一環です。
一歩ずつ、一緒に探していきましょう。
まとめ:「揺れ動く今」は成長の一部
五月雨登校は、決して珍しいことではありません。
特に小学生・中学生という思春期にさしかかる時期は、心も身体も大きく変化する時期。
その変化にお子さん自身が戸惑い、揺れながらも、自分に合ったペースや過ごし方を模索している最中なのです。
たとえ毎日学校に行けなくても、「昨日より1時間早く起きられた」「今日は制服を着てみた」、そんな小さなステップを重ねていることが、すでに前進です。
保護者としては、「このままで大丈夫なのか」と心配になることもあるでしょう。
けれど、今のお子さんを“そのまま”受け止めてあげることこそが、回復と成長の土台になります。
「行ける日もあれば、行けない日もある」
そんな揺れ動く日々を、焦らず、比べず、見守っていけたらきっと大丈夫。
お子さんが自分のペースで、安心して歩き出せるように。
その一歩一歩を、温かく支えていきましょう。
更新日:2025/6/25
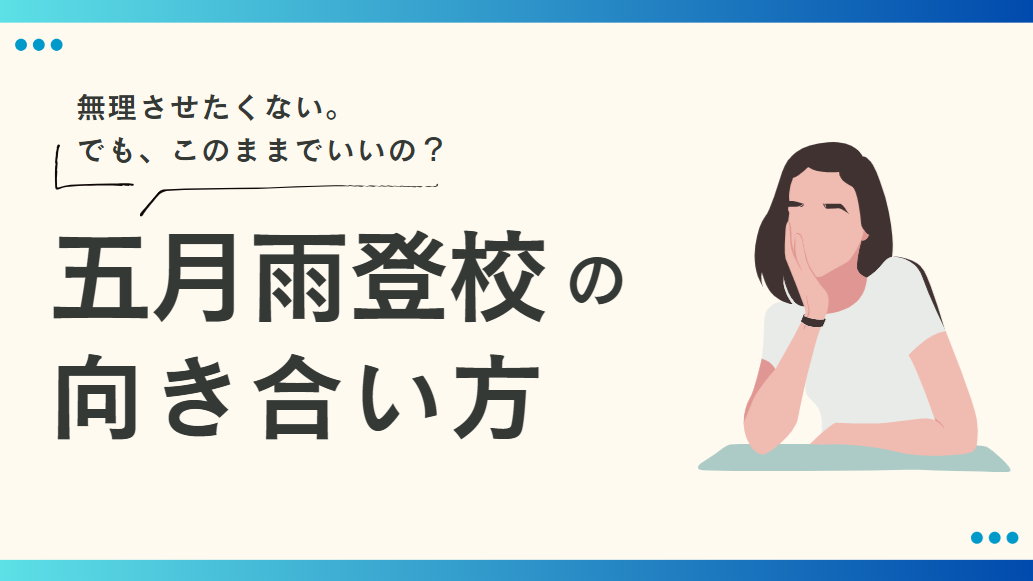

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る