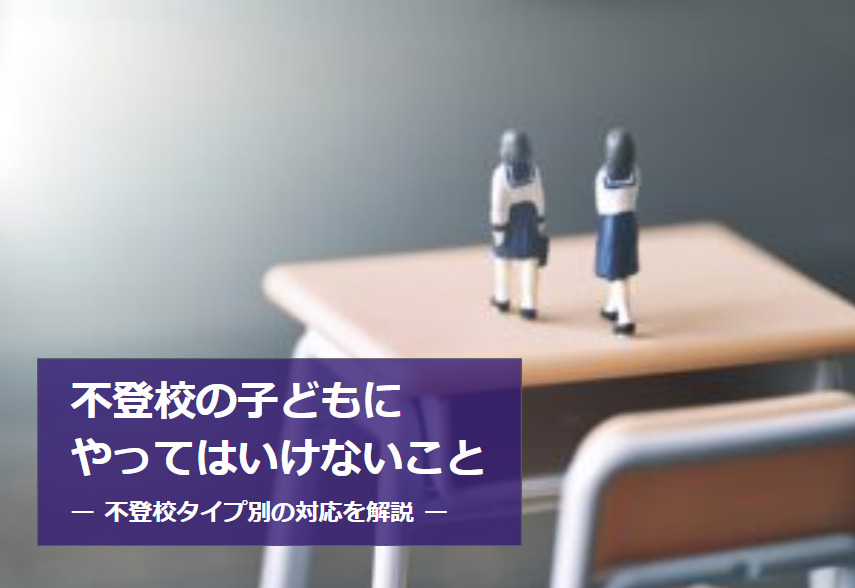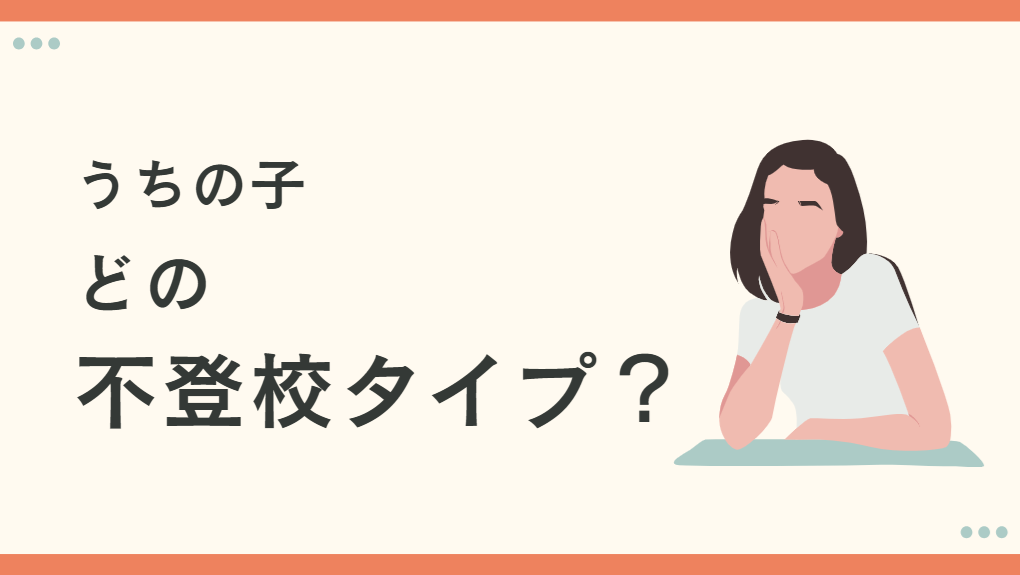「学校に行けていないけれど、勉強はどうしたらいいんだろう……」
「このまま学力が落ちてしまうのでは……」
お子さんが不登校になったとき、そんな不安を抱える保護者は多いのではないでしょうか。
特に「勉強の遅れ」は、目に見える形で不安をあおってきます。しかし、焦りは禁物です。不登校の状態にあるお子さんは、心が疲れていたり、自信を失っていたりする場合が多く、まず必要なのは「無理に勉強をさせること」ではありません。
この記事では、不登校のお子さんを持つ保護者に向けて、ゼロからでも始められる学習のステップと、無理のないサポート体制をわかりやすくご紹介します。
勉強が止まってしまうのは、決して「やる気がないから」「甘えているから」ではありません。心が疲れていると、どれほど簡単なことでも重くのしかかってしまうものです。そんな状態の中で、少しずつでも「学び直すことができるんだ」と実感してもらうためには、寄り添い方や学習の始め方に工夫が必要です。
本記事では、心理的なサポート、学習のステップ、効果的な学習方法、保護者としての関わり方、そして活用できるサービスや教材まで、段階的に紹介していきます。どのご家庭でも無理なく取り組めるよう、実践的なアドバイスを心がけました。
お子さんのペースで、少しずつ前に進むために。
「不登校中の勉強」を一緒に見直し、できることから始めていきましょう。
不登校で勉強が手につかないのは当たり前!まず知ってほしいこと
勉強よりも大切なこと:心のケアと休息
不登校の背景には、友人関係の悩み、学校の雰囲気になじめない、体調不良、発達特性など、さまざまな理由があります。どの理由であっても、共通しているのは「心や体が疲れている」ということ。そんな状態で「さあ勉強しよう!」と声をかけても、エネルギーが足りず、動き出せないのは当然のことです。
まず最優先すべきは、しっかりと休ませること、そして心のケアです。睡眠や食事など生活リズムを整えることから始め、お子さんが「安心できる場所」で過ごせているかを見直してみましょう。勉強は、それが整ったあとでゆっくりスタートしても決して遅くはありません。
無理に勉強をさせようとしないことの重要性
「勉強しないと将来困るよ」
「周りの子はどんどん進んでるよ」
そんな言葉をかけたくなる気持ちもあると思いますが、追い詰める言葉は逆効果です。プレッシャーをかけることで、かえって勉強や将来に対する不安が強まり、余計に動けなくなるお子さんも少なくありません。
勉強は「やらされるもの」ではなく、「自分からやってみよう」と思えることが大切です。まずは「今は休んでも大丈夫」「いつかまた始められる」と伝え、安心感を与えてあげましょう。
自己肯定感を育むことの優先
長く学校に行けていないと、お子さんは「自分はダメなんじゃないか」「普通じゃない」と感じやすくなります。勉強ができないことでますます自信を失い、悪循環に陥るケースも多いのです。
だからこそ、勉強の前に必要なのが「自己肯定感」を育むこと。
「今日はちゃんと起きられたね」
「好きな本を読めたんだ、すごいね」
そんな小さな「できた!」を見つけて、言葉にして伝えてあげることが大切です。
学びは「自分にもできるかもしれない」と思える心の土台があってこそ、初めて前に進みます。勉強を再開する前段階として、この自己肯定感づくりが何よりも大事なステップなのです。
「勉強してない」と感じる子の心理状態
不登校のお子さんは、「勉強していないこと」に対して罪悪感や不安を抱えていることが多くあります。大人が思っている以上に、お子さん自身も「このままでいいのかな」「将来が不安だな」と感じているのです。ここでは、不登校中のお子さんが抱えがちな心理状態と、それに対して周囲がどう関わるべきかを見ていきましょう。
自己嫌悪、不安、無気力感など
「やらなきゃいけないのにできない」
「みんなに置いていかれてる」
「なんで自分はこんななんだろう……」
そんな思いが心の中をぐるぐると巡り、自己嫌悪に陥ってしまうお子さんは少なくありません。さらに、先のことを考えれば考えるほど、「どうせ無理」「もう間に合わない」といった思考に偏り、勉強への意欲を失っていくこともあります。
また、無気力感が強いときは、「やりたい気持ちはあるのに体が動かない」というジレンマも生じます。その状態は、ただの「さぼり」ではなく、心のエネルギーが不足しているサインだと受け止める必要があります。
保護者・周囲の理解と共感の必要性
このような心理状態にあるお子さんに対して、効果的なのはアドバイスよりも共感です。
「やらなきゃって思ってるんだよね」
「しんどいのに、ちゃんと自分のこと考えてるんだね」
そんなふうに気持ちを言語化してもらえるだけでも、お子さんは「わかってもらえた」と感じて安心します。
勉強の前に必要なのは、「勉強してない自分でも受け入れてもらえる」という実感です。叱るのではなく、寄り添ってくれる大人の存在があることが、回復と再スタートへの第一歩になります。
勉強の遅れは取り戻せる!焦る必要はない
不登校の期間が長くなればなるほど、「勉強の遅れが心配」「このままじゃ取り返しがつかないのでは」と焦る気持ちが強くなるかもしれません。ですが、結論から言えば、学習の遅れは取り戻せます。大切なのは、「今どれだけ遅れているか」よりも、「これからどう進んでいくか」に目を向けることです。
スモールステップで始めることの重要性
いきなり「授業に追いつこう」「テストで平均点を取ろう」と目標を立てても、うまくいかないことが多いものです。むしろ、小さく、具体的なステップから始めることが学び直しの近道になります。
たとえば、
朝起きたら10分だけドリルを開いてみる
好きな教科の中の「得意だった単元」だけ復習する
ノートを1ページだけ書いてみる
など、「やればできた」という成功体験を少しずつ積み重ねることが大切です。
「何をどこから始めればいいかわからない」という場合でも、焦らず、「今日できたこと」をひとつずつ増やしていけば、必ず前に進むことができます。
義務教育期間中の学びの柔軟性
日本の義務教育では、一定の出席日数や授業数が求められることはありますが、学び方は決して一つではありません。自宅で学習する、フリースクールを利用する、通信教材を使う――いろいろな方法が認められています。
また、高校進学においても、不登校の生徒を対象にした入試制度(自己推薦、面接重視、内申書の配慮など)を導入している学校も多くあります。つまり、今は「通常の学校に通っていない=将来が閉ざされる」時代ではありません。
柔軟な選択肢があるからこそ、お子さん自身のペースで、自分に合った学びを見つけることが可能です。
「不登校で勉強についていけない」を解消!ゼロから始める学習ステップ
不登校の期間が長くなると、「どこから勉強を始めればいいのかわからない」「もう追いつけないかも…」という不安が出てきます。しかし、学び直しは「今からでも遅くない」どころか、むしろ今が絶好のタイミングかもしれません。
ここでは、ゼロからでも無理なく始められる学習のステップを、具体的に紹介していきます。
現状把握からスタート!どこでつまずいているかを見つける
まず必要なのは、「何がわからなくなっているのか」「どこでつまずいているのか」を知ることです。これをせずに先に進もうとすると、わからない部分が雪だるま式に増え、やる気を失ってしまうこともあります。
▷ 苦手な科目・単元の特定方法
■過去に使っていた教科書やドリルをパラパラとめくって、「知ってる/知らない」で仕分けしてみる
■市販の復習ドリル(学年別)や、オンラインの学力診断を活用してみる
■お子さん自身が「このへんからわからなくなった」と感じたところを本人の言葉で聞いてみる
「どこから勉強すればいいか」ではなく「どこならわかるか」を探すという視点がポイントです。
▷ 学年を遡って復習することの重要性
無理に「今の学年の内容」にこだわる必要はありません。中学2年生でも、小学校の内容からやり直すことで自信を取り戻すケースは多くあります。
わかるところまで戻っていい。
それが、学び直しにとって一番の近道です。
目標設定は「小さく、具体的に」が成功の鍵
「1日5時間勉強する」などの大きな目標は、続かないだけでなく、達成できなかったときに自己否定につながってしまいます。
▷ 短期目標の具体例
「1日15分だけやってみる」
「今日は漢字5個だけ覚える」
「3問だけ計算問題を解く」
小さな目標でも、それが毎日積み重なれば、大きな成果になります。
▷ 本人の「やりたい」気持ちを尊重する
「どの教科から始めたい?」「今日はどれくらいやる?」など、お子さんに選択権を持たせることも大切です。自主性を尊重することで、「自分で決めてやれた」という感覚が育ちます。
無理なく続けられる学習習慣を身につける
「やる気が出たら勉強しよう」ではなく、「やる気がなくても続けられる仕組み」を作ることが、継続の鍵になります。
▷ 毎日決まった時間に勉強する習慣作り
■朝の10時になったら15分だけ取り組む
■寝る前の30分を勉強時間にする
習慣は、「時間」と「行動」をセットにすることで身につきやすくなります。
▷ 集中力を高める環境づくり
■勉強する場所にはスマホやおもちゃを置かない
■短時間ごとに休憩を挟む(ポモドーロ・テクニックなど)
■タイマーやアプリで時間を可視化する
「短く集中→休憩→短く集中」を繰り返すことで、無理なく集中力を維持できます。
▷ 成功体験を積み重ねる工夫
■やったことをチェックリストにして「できた!」を目に見える形にする
■ノートに○をつけたり、シールを貼ったりする
■家族で「すごいね」と声をかけてあげる
「勉強=楽しい」「勉強=できた感がある」というポジティブなイメージをつけることが、長期的なモチベーションにつながります。
不登校中の効果的な勉強方法・学習スタイル
「何をどう勉強すればいいのかわからない」「自宅では集中できない」という声は、不登校のお子さんからよく聞かれます。学校のような時間割や集団授業がないからこそ、自分に合ったスタイルを見つけることが、学習の第一歩です。
ここでは、自宅でも無理なく実践できる効果的な勉強法や学習スタイルを紹介します。
自宅学習の基本!効果的な勉強法
自宅学習の最大のメリットは、「自分のペースで進められること」です。一方で、自己管理が必要になるため、「何をどうやるか」があいまいだと続かなくなってしまいます。
まずは、「インプット」と「アウトプット」を意識してバランスよく取り入れることが大切です。
インプットとアウトプットのバランス(読むだけでなく書く、話す)
「教科書を読んだだけ」「動画を見ただけ」では、頭に残りにくいもの。
インプットしたうえで、それをアウトプットすることで知識として定着します。
▷ 具体的なアウトプットの例:
■覚えたことをノートに書いてみる
■家族に「こんなこと勉強したよ」と話してみる
■小さなテスト形式で自分で確認する
「見る→書く→話す→試す」という流れを意識するだけで、勉強の効果はぐんと高まります。
タイマー学習、ポモドーロテクニックの紹介
集中力が続かない、ダラダラしてしまう、という悩みに有効なのが「時間を区切る勉強法」です。
▷ ポモドーロ・テクニックとは?
■25分間勉強 → 5分間休憩、を1セットとして繰り返す方法
■3〜4セット終えたら、少し長めの休憩(15〜30分)を取る
キッチンタイマーやアプリを使って気軽に始められる方法で、特に集中力に不安があるお子さんにおすすめです。
繰り返し学習の重要性
一度勉強してもすぐに忘れてしまうのは、自然なこと。むしろ、「何度も繰り返すことで定着する」と考える方が現実的です。
▷ 繰り返し学習のコツ:
■同じ内容を3日後・1週間後・1か月後と定期的に復習する
■間違えた問題をまとめておき、あとで見直せるようにする
■「間違えたことは伸びしろ」ととらえて、前向きに復習する
特に不登校中は、時間に縛られずに繰り返せるので、この「ゆとりのある時間」を活かして、理解と定着を重ねていくことがポイントです。
保護者の姿勢:「不登校の子に勉強を教える」際のポイント
不登校のお子さんに勉強を教えるとき、保護者として「どう関わればよいのか」「何を言えばよいのか」と悩む方も多いでしょう。
実は、教える内容よりも“どう接するか”のほうが、はるかに大切です。お子さんの心に寄り添いながら、安心できる環境を整えることで、学ぶ意欲はゆっくりと育っていきます。
ここでは、不登校のお子さんに勉強を教える際に大切にしたい保護者の姿勢について、具体的に紹介します。
焦らせない、プレッシャーをかけない
「このままで大丈夫?」「こんなに勉強してなくて平気なの?」
と、つい口にしてしまいそうになるかもしれません。
でも、その言葉は、すでに不安を感じているお子さんの心をさらに追い詰めてしまうことがあります。
大切なのは、「今のままでも大丈夫だよ」「焦らなくていいよ」と伝えてあげること。
安心感を与える言葉が、お子さんにとっては何よりのサポートになります。
寄り添う姿勢と共感
お子さんが「やりたくない」と言ったときに、「どうして?」と問い詰めるのではなく、
「そっか、やる気にならないんだね」「そういう日もあるよね」と、気持ちを否定せず受け止めることが大切です。
共感の姿勢を持つことで、お子さんは「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じ、少しずつ心を開いていきます。
親子の信頼関係が深まることで、勉強への抵抗感も和らいでいきます。
できたことを具体的に褒める
「すごいね」「えらいね」だけでは、お子さんにとって実感が湧かないこともあります。
「どうすごかったか」「どこがよかったか」を具体的に伝えると、より自信につながります。
▷ 具体例:
「最後まで集中してプリントできたね」
「昨日より丁寧に字が書けてるね」
「嫌だって言ってたけど、5分だけやってみたの、すごいよ」
小さな一歩でも「できた」を積み重ねていくことで、自己肯定感が育ちます。
完璧を求めすぎない
つい「全部できるまでやってほしい」「学校のレベルに追いついてほしい」と思ってしまうこともあるかもしれません。
でも、不登校のお子さんにとっては、「勉強に向かうこと自体がすでに大きな一歩」です。
100点を目指すより、「今日は1問解けた」「10分机に向かえた」という進歩を認めてあげましょう。
“できたこと”に注目する視点を持つことが、継続と回復のカギとなります。
不登校中の勉強をサポートする頼れるサービス・教材
「家庭での勉強に限界を感じる」「どんな教材を使えばいいのかわからない」
そんなときは、外部のサービスや教材の力を借りることが大きな助けになります。
最近は、不登校のお子さんを対象にした学習支援や、自宅で取り組める教材・オンラインサービスが充実しています。お子さんの状態や性格に合ったものを選ぶことで、学びへの一歩を踏み出すきっかけになります。
自宅で学べる!おすすめオンライン学習サイト・アプリ
【無料で使える】気軽に始められるコンテンツ
■文部科学省「子供の学び応援サイト」
教科別の動画やドリルがまとまっており、復習や基礎固めに最適。
■NHK for School
アニメや映像を通して学べるコンテンツ。学年を問わず楽しく学習が可能。
■YouTubeの学習チャンネル(とある男が授業してみた、学研チャンネルなど)
中高生に人気。先生の話し方や内容が親しみやすく、繰り返し見やすい。
【有料の定番サービス】学年や目的に応じて選べる
■スタディサプリ
月額2,178円。短時間で学べる動画授業が好評。
■進研ゼミ
紙とタブレット両方のコースあり。教材量が豊富で、添削指導も受けられる。■易度は高め。思考力を養いたい子に向いている。
■すらら
不登校のお子さん向けに設計されたインタラクティブ教材。理解度に応じて出題が変わり、学年にとらわれず学べる。
▷ 選び方のポイント
「わかるところから始められる」か
「教科・学年を自由に選べる」か
「毎日の負担にならない仕組み」かどうか
基礎固めに最適!市販の教材・問題集
デジタルが苦手なお子さんや、紙でじっくり取り組みたいお子さんには、市販の教材がおすすめです。
▷ 選び方のヒント
「わかるところから」「学年にこだわらない」教材を選ぶ
「1冊が薄く、達成感を得られやすい」ものを選ぶ
▷ おすすめのシリーズ
■学研「毎日のドリル」シリーズ
1冊500円程度で、基礎的な内容を効率よく復習できる。
■くもん出版「小学○年の漢字・計算」シリーズ
繰り返し学習に最適。短時間でも取り組みやすい。
■旺文社「中学総復習」「中学一問一答」シリーズ
中学生向けに、要点を効率よく復習できる設計。
個別指導・家庭教師
「一人では難しい」「教えてくれる人がいると助かる」
そんなときは、家庭教師や個別指導の活用も効果的です。
▷ メリット
お子さんのペースや性格に合わせた対応が可能
質問しやすく、対話を通じて理解が深まりやすい
自信や自己肯定感につながる声かけが得られる
▷ 不登校対応のサービス例
オンライン家庭教師Wam(不登校専門コースあり)
家庭教師のトライ(不登校サポートあり)
メガスタ(オンライン型で全国対応)
▷ 注意点
お子さんが「話しやすい」「信頼できる」と思える講師との相性が重要
「勉強を強制しすぎない」「心のサポートもしてくれる」姿勢のあるサービスを選ぶこと
フリースクール・適応指導教室の活用
勉強と居場所の両方を求めている場合は、フリースクールや適応指導教室の利用も検討しましょう。
▷ 利用時のポイント
いきなり通うのではなく、見学や体験から始めてみる
お子さん自身が「ここなら通えそう」と感じられる場所を選ぶ
▷ オンラインのフリースクールも
オンラインフリースクール「シンガク」は、不登校や学校に通いづらいお子さんたちのための完全オンライン型の学習支援・居場所提供サービスです。
週5日通えるオンラインの居場所、少人数制&対話中心の授業、一人ひとりに合わせた学習支援、在籍校との連携といった特徴があります。
まとめ:心の回復を最優先に、前進は一歩ずつ
不登校のお子さんにとって、勉強は「やるべきこと」であると同時に、「心のハードル」でもあります。保護者としては将来を思い、勉強の遅れを心配するのは当然のこと。しかし、焦りや不安をそのままぶつけてしまうと、お子さんはますます自信を失ってしまいます。
大切なのは、今の状態をそのまま受け入れ、心の回復を最優先にすること。
そのうえで、お子さんの気持ちとペースを尊重しながら、小さなステップで学びを再開していけば、勉強は必ず取り戻せます。
また、学ぶ方法は学校だけではありません。家庭での学習、市販の教材、オンラインサービス、家庭教師、フリースクール……。今は、多様な選択肢の中から「自分に合った学び方」を見つけられる時代です。
保護者がすべてを抱え込む必要はありません。周囲の力やサービスを借りながら、お子さんの「わかる」「できた」「やってみたい」という気持ちを少しずつ育んでいきましょう。
「学校に行っていない=学んでいない」ではありません。
お子さんにとっての「学び」は、これからいくらでも育て直せます。
焦らず、寄り添って、一緒に前に進んでいきましょう。
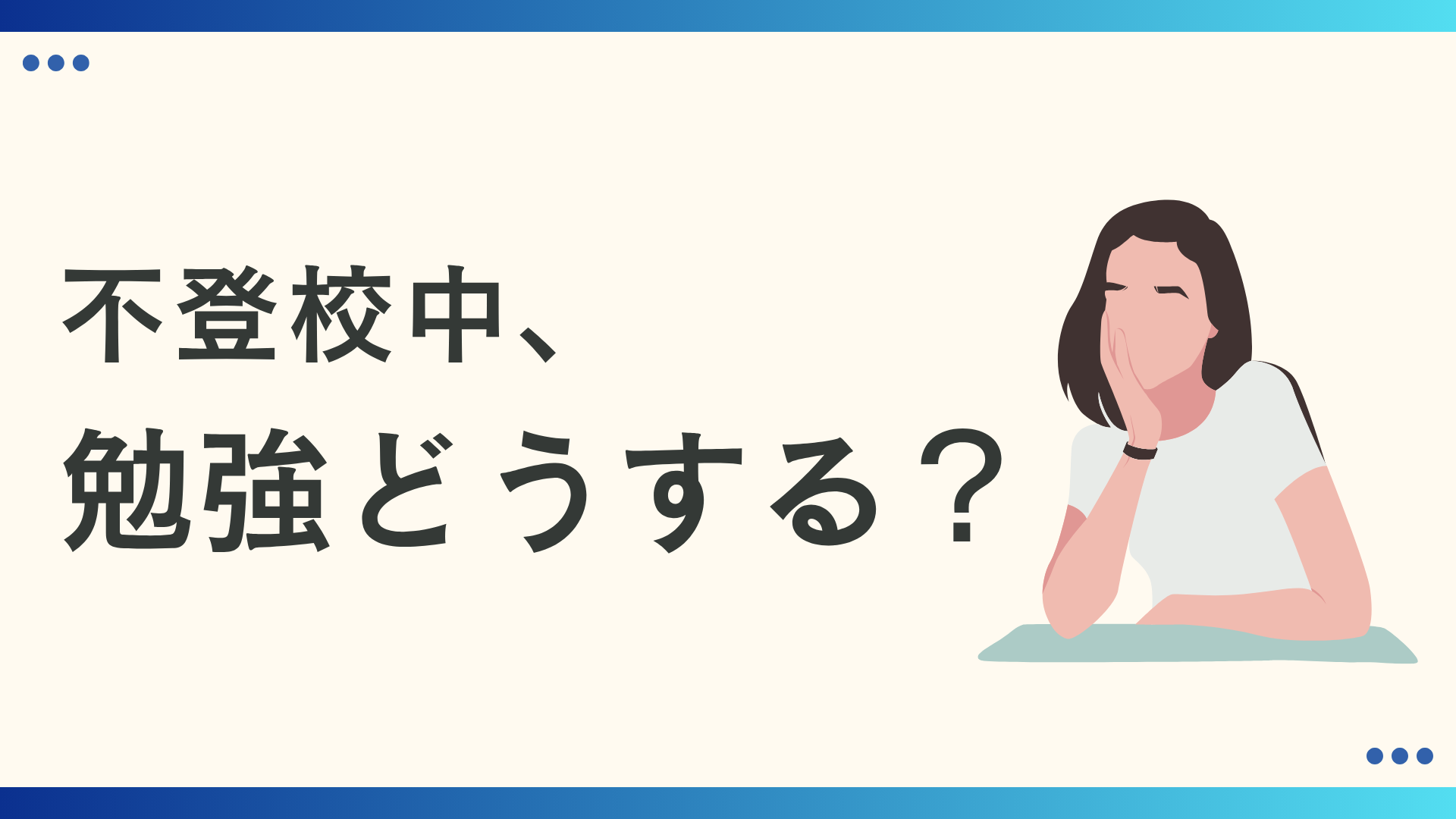

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る