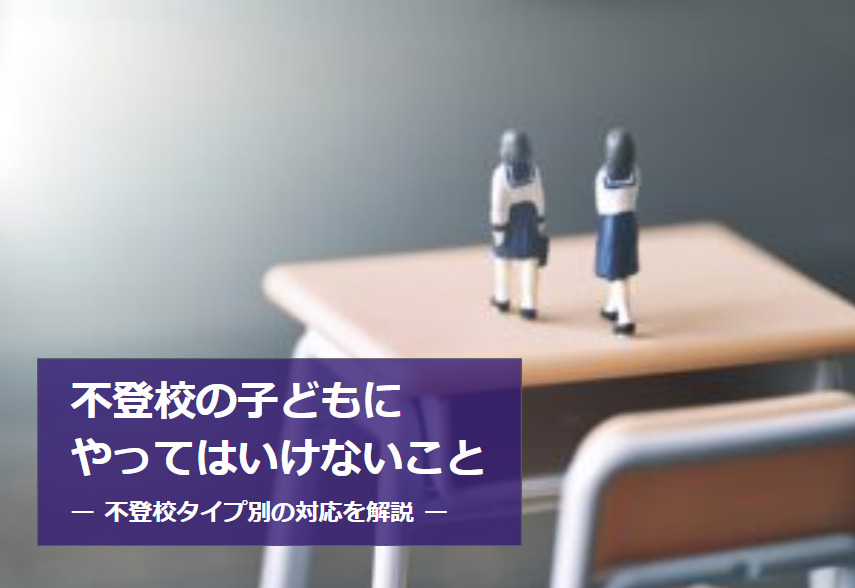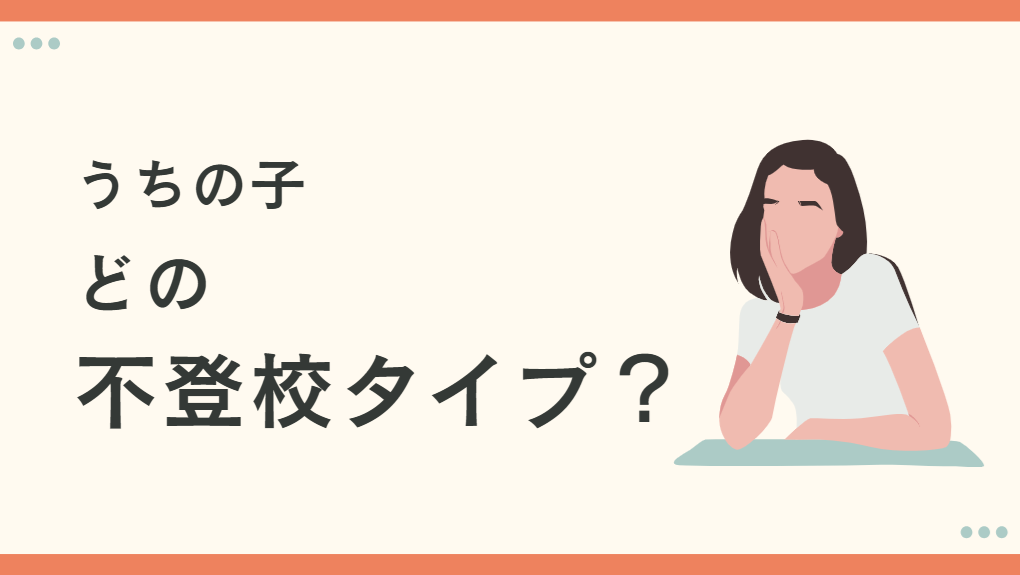長い夏休みが終わり、いよいよ新学期。
ランドセルを背負って元気に登校する子どもたちの姿が見られる一方で、「学校に行きたくない」「体調が悪い」と言い出すお子さんに戸惑うご家庭も少なくありません。
夏休み明けは、実はお子さんの心に大きな負担がかかる時期。
生活リズムの変化や学校生活への不安から、心や体にSOSを出すお子さんもいます。
そんなとき、周囲からは「甘えてるだけじゃない?」「怠け癖では?」と見られることもあるかもしれません。しかし、不登校は決して「怠け」ではなく、お子さんが無理をしすぎた結果として現れるサインです。
この記事では、「夏休み明けになると登校がつらくなるのはなぜ?」「子どもにどんなサインが出るの?」「親としてどう関わればいいの?」と悩む保護者の方に向けて、夏休み明けの不登校の兆しとその対処法をわかりやすく解説します。
始業式前後のつらさの背景や、再登校を焦らず支えるための7つのヒントも紹介しています。
お子さんの気持ちに寄り添いながら、少しでも前向きな一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。
なぜ夏休み明けに不登校になる子が多いのか?
環境の急変がストレスになる
夏休み中は、お子さんにとって「自由」と「安心」に満ちた時間です。朝はゆっくり起きて、好きなことをして過ごす。家族とリラックスして過ごす時間が多く、ストレス要因が少ない状態です。しかし、休みが明けた途端、早起き・制服・宿題・集団生活・ルール…と、まったく異なる環境に急激に戻る必要があります。
この急変が、子どもにとって大きなプレッシャーになります。特に、元々学校に不安を感じていたり、友人関係や学業面でつまずきがあったりするお子さんにとっては、「またあの場所に戻る」という現実が重くのしかかります。
「夏休み しんどい」「夏休み つらい」と感じていたお子さんは、夏休みが終わることで解放感から一転、不安とストレスの渦に巻き込まれてしまうのです。
「学校がしんどい」本音を言えないまま我慢して通っていた子ほど限界を迎えやすい
実は、夏休み前まで「普通に登校していた」お子さんの中にも、実は心が悲鳴を上げていたケースは少なくありません。
周囲には笑顔を見せつつも、心の中では「学校がつらい」「勉強についていけない」「友達とうまくいかない」と悩みを抱えているお子さんがいます。
こうした子は、自分でもつらさをうまく言葉にできなかったり、「言っても仕方ない」と諦めていたりすることが多く、我慢を重ねて登校してきたのです。
夏休みは、そうした「無理」がいったんリセットされる期間。その結果、「もうあの生活には戻れない」と感じてしまい、始業式を前にして不調が現れることがあります。
親から見ると「突然行けなくなった」ように見えても、実はそれ以前から小さなサインが出ていたこともあります。お子さんの表情や言動の変化に、敏感に気づいてあげることが大切です。
始業式がひとつのハードルに
始業式は、休み明けの最初の大きなイベントです。通常の授業とは異なるとはいえ、大勢の子が一堂に会し、長時間座って話を聞くなど、学校生活への再スタートとしては負荷の高い日です。
また、始業式に「元気に登校すること」が良しとされる雰囲気の中で、気持ちがついていかないお子さんは強い不安を感じます。「また今日から毎日学校があるのか」「友達にどう思われるだろう」「先生に怒られないかな」といった思いが膨らみ、当日の朝に体調不良や拒否反応として表れることもあります。

夏休み中・明けに見られる不登校のサイン
お子さんが学校に行きたくないと感じていても、それを言葉で表現するのは簡単なことではありません。多くのお子さんは「行きたくない」とは言えずに、さまざまなサインとして不調を表します。そのサインは一見するとわかりにくく、見過ごされがちです。
たとえば、
・朝なかなか起きられない
・食欲がない
・頭痛や腹痛を頻繁に訴える
といった身体症状があります。
病院では異常が見られないことも多く、「仮病?」と疑いたくなるかもしれませんが、これは体が感じているストレスが身体症状として現れている状態です。
また、家庭内での行動にも変化が見られることがあります。
・ゲームやスマホに過剰に依存する
・家族との会話が極端に減る
・表情が乏しくなる
・何に対しても無気力になる・イライラしやすくなる
などの様子が見られたら、心の中に不安やストレスを抱えている可能性が高いです。
これらのサインに早く気づくことが、不登校の長期化を防ぐ第一歩になります。「変だな」と思ったら、叱るのではなく、そっと「最近、どう?」と話しかけてみてください。
夏休みが終わる頃、「学校行きたくない」とはっきり言うお子さんもいれば、言葉では表現できずに体調不良という形で現れる子もいます。
以下のような兆しが見られる場合、不登校のサインかもしれません。
■朝起きられない、起きても動けない
■頭痛や腹痛などの身体症状(病院でも異常なし)
■表情が暗い、やる気がない
■ゲーム・スマホに依存気味
■家族との会話が減る、急に怒りっぽくなる
これらのサインは、「学校に行きたくない」という気持ちを必死で押し殺している表れです。まずはお子さんの状態に目を向け、安心できる声かけから始めてみましょう。
夏休みの過ごし方が登校に影響する?
自由度が高い夏、心がほぐれる子もいる
夏休みは学校という枠を離れ、自分のペースで生活できる貴重な時間です。
なかには、「学校では見せられなかった本来の自分」を取り戻せたと感じるお子さんもいます。絵を描く、本を読む、自然に触れるなど、心が豊かになる経験ができた場合、学校に戻ることで再び「無理をする日々」が始まることに強い抵抗を覚えるのです。
反対に、休み明けがつらくなることも
夏休み中に昼夜逆転、外出を控えた生活が続いた場合、学校生活へのギャップが大きくなりすぎて「もう戻れない」と感じるお子さんもいます。特に、SNSやゲームの世界に没入していた場合、現実の人間関係への不安が一気に押し寄せます。
このようなとき、「だらけていたからだ」と叱るよりも、「戻るのが怖くなってるんだね」と気持ちを受け止める姿勢が大切です。

親ができる7つのサポート方法
1. 子どもの不安を否定しない
「そんなことで?」「行けばなんとかなるよ」と言う前に、「つらいんだね」と気持ちに共感を。
2. 「行けるようになる」がゴールでなくていい
まずは家で安心して過ごせる状態を目指しましょう。無理な登校より、心の安定が優先です。
3. 朝の過ごし方を工夫する(登校圧の軽減)
朝は怒らず静かに声をかける、着替えや朝食など小さなステップだけ促す、など登校の圧を減らすことがポイント。
4. 学校以外の安心できる場所を見つける
フリースクール、地域の学習支援室、オンラインの居場所など、お子さんが安心できる環境を探しましょう。
5. プロに相談する
スクールカウンセラーや教育相談機関に早めに相談を。専門家の視点が親子を救ってくれることもあります。
6. 他の保護者とつながる
同じ悩みを持つ保護者との交流は、孤独感や不安を軽減する助けになります。
7. 保護者自身のストレスケアも大切
保護者が疲れてしまうと、お子さんにも伝わってしまいます。自分自身のメンタルケアも忘れずに。
冬休み明けにも同じことが起こる?
不登校は夏休み明けだけでなく、冬休み明けや春休み明けにも起こる可能性があります。
特に冬は日照時間の短さや寒さで心身のバランスを崩しやすく、「布団から出られない」「無気力になる」といった状態になりがちです。
また、年末年始は家族との時間が増え、学校との距離を感じやすくなる時期。冬休み明けも、お子さんの様子に変化がないか注意して見守りましょう。

登校できないときの代替案と支援
無理して学校に行かなくてもいい場合も
学校に行くことがどうしてもつらい場合、無理に登校させるよりも「一時的に休む」「別の学び方を選ぶ」という選択肢もあります。
・フリースクール
・オンライン家庭教師・通信教育
・在籍校との連携による出席扱い制度(自治体によって対応あり)
など、まずは「安心できる環境」で再スタートすることが、結果的に自信と意欲を育てます。
保護者も孤立しないで
「うちの子だけ…」「自分の育て方が悪いのでは」と思い詰めてしまう保護者もいますが、今や不登校は特別なことではありません。
各自治体の教育相談センターや、不登校支援団体、保護者同士のピアサポートなど、つながれる場所はたくさんあります。必要なときは、遠慮なく頼ってください。
まとめ:無理に解決しようとせず、長い目で寄り添う姿勢を
夏休み明けの不登校は、決してめずらしいことではありません。
「行けなくなった」ことばかりに目を向けるのではなく、「何に困っているのか」「どうすれば安心して過ごせるのか」を一緒に考えることが大切です。
お子さんの将来は、今の一歩で決まるわけではありません。焦らず、長い目で、親子で歩んでいきましょう。
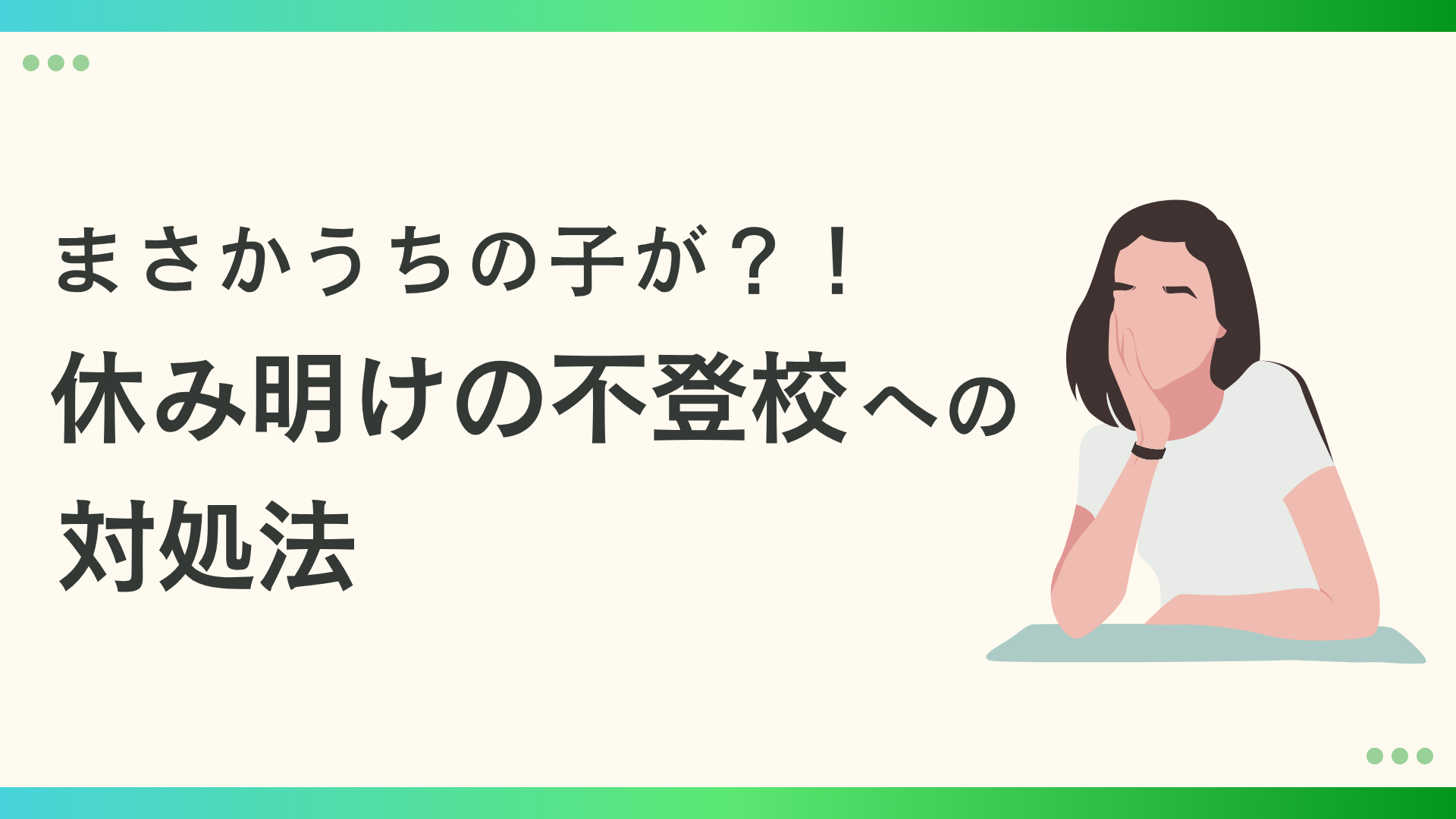

 つぶやく
つぶやく シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る